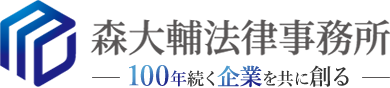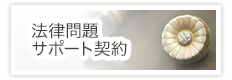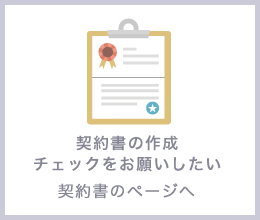労務問題
1.当事務所の労働事件への取り組み
当法律事務所では、使用者側の代理人として従業員とのトラブルに関する事案を数多く対応してきております。使用者側からのご相談の中で、問題社員にどのような懲戒権の行使ができるかという相談(主に解雇ができるかという相談)が非常に多いです。
普通解雇する場合には、労働契約法16条の解雇権乱濫用による制限がありますし、懲戒解雇にとなれば就業規則上の根拠から弁明の機会の付与を与える等の厳しい制限があり、事案によってはそれ以外の処分で対応すべきものも多くあります(それらの処分の積み重ねとして解雇が有効にできることもあります。)。
そのため、普通解雇や懲戒解雇を行う場合は、本当にそのような処分をすることが必要なのか十分な議論が必要です。ケースによっては、使用者側の管理監督に問題が認められることもあります。このような場合に、無理に解雇や他の懲戒権の行使を行うとなると他の従業員と会社との信頼関係は損なわれる一方です。当事務所では、適切な懲戒権の行使のアドバイスを常に心がけております。
また、次に多い相談としては、未払残業代に関するものが挙げられます。労働者側から未払残業代の支払いを請求された場合、殆どの事案で勝てないと言われております。しかしながら、労働者の働き方を細かく精査すると、会社からの拘束下を逃れた環境において自由な時間を過ごしているということも少なくありません。当事務所ではこのような事実関係に関する調査を行い、適正な残業代を計算し直し、不当に残業代を請求されないための対策も取っております。
2.懲戒権・解雇
労働事件で特に相談が多いのが、普通解雇や懲戒解雇(その他懲戒権の行使)に関するものです。普通解雇は懲戒権の行使ではないので、懲戒解雇とはその性質を異にしますが、どちらを処分として採るべきかということは、時として非常に悩ましい問題を含んでおります。普通解雇と懲戒解雇を含む懲戒権の行使について説明致します。
①懲戒権の行使としてはどのようなものがあるか。
会社側は、長期雇用が保障されている従業員(正社員や無期社員)に対して、懲戒権を行使することができます。懲戒権とは、企業秩序に違反した労働者に対する制裁罰のことを言います。懲戒権の行使をしなければならないケースとしては、あまりにも酷い問題社員がいる場合が挙げられます。従業員や労働組合から反論を恐れて何もしないと、他の真面目に働いている従業員が不平等さを感じ、職場全体の士気にも影響しかねません。
懲戒権の種類としては、戒告・けん責、減給、出勤停止、昇給昇格の停止や降格・降職、論告退職、懲戒解雇が挙げられます。
但し、これらの懲戒権の行使は就業規則等において懲戒事由を予め定めていなければなりませんので、就業規則の作成等は懲戒権を行使する前提として非常に重要となってきます。
②懲戒解雇と普通解雇の関係
・懲戒権濫用の法理(労働契約法15条)
まず、懲戒権解雇を含む懲戒権の行使については、相当性、公平性、適正手続が求められ(ダイハツ工業事件参照)、慎重な対応が求められます。また、懲戒権の行使については、就業規則上の根拠も求められますので、就業規則をどのように定めるかという点も重要となってきます。
・懲戒解雇を行うためには、その要件が非常に厳しいため、懲戒解雇事由があったとしても、敢えて普通解雇で対応すべき場合もあります。そこで、懲戒解雇事由がある場合に普通解雇ができるかという相談がよくあります。
この点については、就業規則の規定の仕方がどうなっているかがポイントとなります。懲戒解雇事由を普通解雇事由に挙げていれば普通解雇は可能です。近時の就業規則では概ねそのような規定の仕方となっているように思われます。
・懲戒解雇は極めてハードルが高いため、適法だと認められない判断が下されることが多いです。そのような場合、懲戒解雇から普通解雇への転換ができるかが問題となります。
この点、懲戒解雇は懲戒権の行使であり、他方で普通解雇は私法上の形成権の行使であると言われています。このように、両者は性質を異にするものなので、基本的には転換はできないと言われています。但し、懲戒解雇は無効としながらも、懲戒解雇の意思表示には普通解雇の意思表示を含むものと判断した裁判例(東京地判昭和45年6月23日労判105号39頁、東京高判昭和61年5月29日労民37巻2号257頁)もありますので、実務上は、懲戒解雇を行う際、解雇通知書の中で予備的に普通解雇の意思表示も行っておくことも検討すべきだと思われます。こうすることで、バックペイの発生も防ぐことができます。
③懲戒解雇と退職金との関係
退職金規定に懲戒解雇された者に対する退職金の不支給・減額の規定を置いていても、それが権利の濫用と認定されるケースがあります。退職金を支給しないことが認められるためには、永年の勤労の功を抹消してしまうほどの重大な背信行為があったことが必要となります。
→痴漢行為で懲戒解雇となったケースの紹介
小田急電鉄事件(東京高判平成15年12月11日判時1853号145頁)
「本件行為が悪質なものであり、決して犯情が軽微なものとはいえないこと、また、控訴人は、過去に3度にわたり、痴漢行為で検挙されたのみならず、本件行為の約半年前にも痴漢行為で逮捕され、罰金刑に処せられたこと、そして、その時には昇給停止及び降職という処分にとどめられ、引き続き被控訴人における勤務を続けながら、やり直しの機会を与えられたにもかかわらず、さらに同種行為で検挙され、正式に起訴されるに至ったものであること、控訴人は、この種の痴漢行為を率先して防止、撲滅すべき電鉄会社の社員であったことは、上記……記載のとおりである。
このような面だけをみれば、本件では、控訴人の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があったと評価する余地もないではない。
しかし、他方、本件行為及び控訴人の過去の痴漢行為は、いずれも電車内での事件とはいえ、会社の業務自体とは関係なくなされた、控訴人の私生活上の行為である。そして、これらについては、報道等によって、社外にその事実が明らかにされたわけではなく、被控訴人の社会的評価や信用の低下や毀損が現実に生じたわけではない。なお、控訴人が電鉄会社に勤務する社員として、痴漢行為のような乗客に迷惑を及ぼす行為をしてはならないという職務上のモラルがあることは前述のとおりである。しかし、それが雇用を継続するか否かの判断においてはともかく、賃金の後払い的な要素を含む退職金の支給・不支給の点について、決定的な影響を及ぼすような事情であるとは認め難い。」
④ 普通解雇について
・普通解雇の制限
普通解雇事由に該当する事実があったとしても、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」(労働契約法16条)は、解雇権濫用として解雇そのものが無効となるケースがあります。そのため、普通解雇と言えども自由に行える訳ではありません。
・就業規則上の根拠が必要であること
普通解雇事由についても、就業規則における絶対的記載事項とされておりますので(労基法89条3号)、就業規則上の根拠を作る必要があります。そのため、網羅的に解雇事由を規定するための工夫として、就業規則には概括的な解雇事由を入れておくことが考えられます。例えば、「会社の従業員として適格性がないとき」などです。他方で、「その他上記各号に準ずる具体的事由があるとき」という規定の仕方もよく見受けられます。しかしながら、このような規定では、結局は具体的列挙事由と同じものということになるので、あまり効果がないと思われます。
なお、就業規則上の文言で、使用者自ら解雇を制限するような文言となっていないか注意することが必要です。例えば、「著しく」や「再三」などの表現は自らの立証のハードルを上げることとなるので、このような表現は避けるべきです。
・能力不足を理由に解雇ができるか
従業員に非違行為がある訳ではなく、能力不足(勤務成績)を理由とする解雇ができるかという相談はとても多いです。この点について、注意が必要なのが、成果主義を採用している会社です。会社が成果主義を採用している場合は、業績の低さが使用者に与える不利益の程度が軽減されることになるため、成績や労働能力を理由とする解雇はより厳しく制限されてしまいます。そのため、成果主義を導入することは、普通解雇との関係でよりハードルが上がるため注意が必要となります。
・期間の定めのある雇用契約の場合の解雇
雇用期間の途中で契約を打ち切ることは解雇となりますが、その場合、労働契約法17条1項で「やむを得ない事由がある場合でなければ」解雇できないと規定されております。これは解雇権濫用法理(労働契約法16条)における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められる場合よりも狭いと解されており、より厳格な要件を満たす必要があります。
他方、期間が満了後の雇止めの場合は、解雇権濫用法理の考え方が取り入れられています(労働契約法19条)。
・解雇が無効であった場合、賃金や賞与、手当はどのように処理されるのか
賃金については民法536条2項の債権者主義が適用されるので、バックペイが発生してしまいます。但し、各種手当(通勤手当等)は、実際に通勤していないので発生はしません。
では、賞与はどうでしょうか。この点については、就業規則の条項の解釈にもよるところが大きいと言われています。そもそも、賞与は、人事査定があって具体的権利となるものです。その査定がないのに発生するということは基本的には困難と言わざるを得ません。但し、一定額を認める裁判例も存在します。例えば、就業規則に「別表の手当支給表に定める手当を支給する」と規定されているような場合は評価が異なるとされています。
(参考判例:東京地裁平成6年11月15日労働判例666号32頁)
「賞与は、労働基準法11条所定の労働の対価としての広義の賃金に該当するものであるが、その対象期間中の企業の営業実績や労働者の能率等諸般の事情により支給の有無及びその額が変動する性質のものであるから、具体的な賞与請求権は、就業規則等において具体的な支給額又はその算出基準が定められている場合を除き、特段の事情がない限り、賞与に関する労使双方の合意によってはじめて発生すると解するのが相当である。
これを本件についてみるに、成立に争いのない(証拠略)によれば、被告の「服務規定」第二七条は、「賞与は、年二回、七月及び十二月に左の通り支給する。但し、支給額は、その勤務成績、勤続年数及び会社の業務成績等により増減することがある。尚、勤続六ケ月未満の者及び前半期の出勤日数が八割に満たない者に対しては減額する。七月・基本給の0・五ケ月分、十二月・基本給の一ケ月分」と規定していることが認められるところ、右規定が「支給額は、その勤務成績、勤続年数及び会社の業務成績等により増減することがある。」と定めているから、これによって直ちに具体的支給額が算出されるものではない。」
コロナ禍における整理解雇
新型コロナウイルス感染拡大によるリストラクチャーの一環として整理解雇を検討される企業様もいらっしゃるかと思います。整理解雇を行う場合には考慮要素がたくさんあるため、不用意に整理解雇を行うことはリスクが大きいと言わざるを得ません。特に訴訟リスクについては企業が甚大な被害を受けることもあります。新型コロナウイルスなど有事における「整理解雇」について纏めていますので、詳しくはコチラをクリックしてご覧ください。
3.未払残業代請求に対する対応
① 残業代請求がきたときの初期動作注意点
・付加金への注意
付加金とは、残業代等が未払いの場合に、労働者の請求により、裁判所が使用者に対して、未払金とは別に支払いを命じることができる金銭をいい、その額は未払金と同一とされています(労働基準法114条)。
従業員側から未払残業代の支払いを求める内容証明郵便が届いたときは、まずは、使用者側に一方的に非があるような事案なのか、そうでない事案なのか、見極めることが必要となってきます。使用者側に一方的に非がある場合には、付加金を意識する必要があるため、早めに話し合いでの解決を試みる必要があります。
・労働者側の要求への対応
労働者側からは残業代請求の金額も定まらないのに、タイムカードや就業規則、労働マニュアル等を提出せよと要求してくることが多々あります。確かに、残業代請求の一時的な立証責任は労働者側が負っていますが、使用者側は労働時間を管理する義務を負っています。では、使用者としては、どこまで労働者側の要求に対応する必要があるのでしょうか。
この点については、以下の裁判例が参考となります。
「時間外労働等を行ったことについては、同手当の支払を求める労働者側が主張・立証責任を負うものであるが、他方で、労基法が時間外・深夜・休日労働について厳格な規制を行い、使用者に労働時間を管理する義務を負わせているものと解されることからすれば、このような時間外手当等請求訴訟においては、本来、労働時間を管理すべき使用者側が適切に積極否認ないし間接反証を行うことが期待されているという側面もあるのであって、合理的な理由がないにもかかわらず、使用者が、本来、容易に提出できるはずの労働時間管理に関する資料を提出しない場合には、公平の観点に照らし、合理的な推計方法により労働時間を算定することが許される場合もあると解される。」(スタジオツインク事件・東京地判平成23年10月25日労判1041号62頁)。
この裁判例を前提とすれば、使用者側がタイムカードや就業規則、労働マニュアル等の提出を拒むことには相当なリスクがあると言わざるを得ません。結局は、最終的に裁判所からも提出を求められるものであることを考えると、これらについては早期に提出をすることが望ましいと言えます。
②残業代請求に対する対応方法
労働時間性を争う使用者側としては、労働時間性が否定される要素がないか十分な聞き取りが必要となります。きちんとした労働時間性が認定される場合には、労働者の権利でもありますので支払いは必要となりますが、労働を放棄する等労働時間性が認められないのにこれを労働時間として扱う不当な請求に対しては、毅然とした対応で臨むべきである。
この点について、労働時間性が認められるかどうかについては、以下のような考え方で判断されることとなります。
まず、拘束時間外であれば、原則、労働時間にあたりませんが、業務遂行に関する指示やそのための拘束がなされていれば、それは労働時間となり得ます。
他方、拘束時間内であっても、労働が義務付けられておらず、休憩と同様に労働からの解放が保証されていると評価できる例外的な事情があれば労働時間にあたらないと考えるべきです。
なお、タイムカードやICカードのような証拠としての価値が高いとされるものについては、その記載時間そのものが労働時間と推定されてしまうことには注意が必要です。なぜなら、タイムカードには承認印が押されていたり、それを根拠に給与計算などをしていたりするからです。逆に言えば、承認印が押されていなかったり、給与計算の根拠となっていなかったりする場合はこのような推認は働かないこととなります。その場合は、タイムカードと労働実態が一致するものでないこと(例えば、就業時間後には労働からの解放が保証されていた事情があること等)を反論すべきこととなります。
4.テレワークと労務管理
新型コロナの影響で、令和2年4月7日、政府より緊急事態宣言が発令され(7都府県を対象。4月16日に全国を対象に発令されました。)、同月11日には安倍晋三首相から「出勤者を最低でも7割は減らす」との要請もあり、労働環境は大きく変化しています。ところが、テレワークを導入したいと思っていても、突然のことで、何から始めればよいかが分からないという会社も多くあると思います。
そこで、テレワーク(ここでは「在宅勤務」の意味に絞って使用します。)を導入するにあたり、何をすればよいかについて、労務管理の観点からお伝えしたいと思います。
1.テレワークを導入すると、なにが変わるの?
そもそも、テレワークを導入すると、これまでと何が変わるのかについて考えていきたいと思います。
テレワークを導入すると、労働者は自宅で業務を行うことになりますので、使用者は、労働者がいつからいつまで働き、今どのような業務を行っているかについて、直接見て確認することができません。
テレワークといえども、時間外に業務を行えば割増賃金が発生しますし、それが深夜まで及べば深夜割増賃金が発生します。また、各労働者に業務量のミスマッチが起こっていると、納期までに業務を完了できなくなるかもしれませんし、労働者間で不公平感を感じさせることになりかねません。
そこで、以下では、まずテレワークの導入に当たり労基法上の留意点を説明したのち、①労働者の労働時間の把握、及び②業務の進捗状況の把握について説明したいと思います。
2.テレワークを導入しても、労働基準法の適用は受けるの?
テレワークを導入しても、会社と従業員が使用者と労働者の関係にあることに変わりはありませんので、労働基準法の適用はもちろん受けることになります。
テレワークの導入に当たり、労基法上の留意点は以下の点になります。労基法上、就業規則の変更が必要となる点に注意が必要です(常時10人以上の労働者がいる会社の場合)。
就業規則の変更方法は、既存の就業規則にテレワーク用の条項を盛り込む方法もありますが、「テレワーク勤務規程」のようにテレワーク用の就業規則を別途設ける方法もあります。
・労働条件の明示
使用者は、労働契約締結の際、労働者に就業場所を明示する必要があります(労基法15条1項、労基法施行規則5条2項)。在宅勤務であれば、就業場所を従業員の自宅と明示することになります。
・労働時間の把握
使用者は、労働時間を適正に管理するため、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準・平成13年4月6日基発第339号)。この点は、割増賃金等が発生するか否かの管理にも関わります。
・業務評価・人事管理等の取り扱い
業務評価や人事管理について、会社へ出社する労働者と異なる取り扱いをする場合は、その内容を丁寧に説明する必要があります。
また、就業規則の変更手続が必要となります(労基法89条2号)。
・通信費・情報通信機器等の費用負担
通信費・情報通信機器等の費用負担については、あらかじめ決めておく必要があります。なお、これらの費用を労働者に負担させる場合は就業規則に規定する必要があります(労基法89条5号)。
・社内教育の取り扱い
テレワーク中の労働者に社内教育や研修制度に関する定めをする場合も、当該事項について就業規則で規定する必要があります(労基法89条7号)。
3.労働者の労働時間を把握するためには?
労働者の労働時間を把握するためには、ⅰ)始業・終業時刻の管理と、ⅱ)業務時間中の在席確認の二つの視点でとらえる必要があります。
3-1.始業・終業時刻の管理
すでに述べましたが、これまでのように労働者が会社に出社して業務を行うのであれば、使用者も、いつ、誰が出社し、退勤したのかがわかります。会社に備え付けられているタイムカードや、社用のパソコン内の勤怠管理システムで勤怠を管理している会社も多いことでしょう。ところが、テレワークになると誰がいつからいつまで仕事をしているのかがわかりません。そこで、始業・終業時刻を管理するルールを労使間で決める必要があります。
労働時間の管理については、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を出しており、テレワークを導入する場合もこのガイドラインに準拠する必要があります。
労働時間は、使用者が労働者の労働日ごとの始業・終業を確認する必要があります。そこで、原則としては、使用者自らが現認して確認したり、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録で確認することになります。
しかし、テレワークのようにやむを得ず労働者の自己申告制で労働時間を確認する場合、例外的に、以下の措置を講ずる必要があります。
・自己申告を行う労働者や労働時間を管理する者に対しても、自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
・自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
・使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと、さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること
以上のように、労働者の自己申告制で労働時間を把握する場合であっても、得られた資料から適正に労働時間を把握することが求められます。
したがって、労働者から始業・終業をメールで伝える方法や、オンライン上で勤怠管理ができるツールを利用するなどして、労務管理の方法を新たに取り決める必要があります。
|
・POINT 始業・終業時間の連絡方法を、労使でルール化することが大切。 |
3-2.業務時間中の在席確認
会社に出勤をして業務をする場合、労働者も休憩時間中以外は業務を行っていると思います。ところが、テレワークになると常に業務をしているか使用者側から分からなくなるのはもちろん、育児や介護のため保育園や病院への送迎を日中に行うなど、労働時間中に業務から離れる時間を設けたいというニーズが労働者から寄せられるケースが考えられます。つまり、労働時間中の在席確認のルールを取り決めるとともに、業務から離れる時間(私用の時間)の扱いをどうするかを取り決める必要があります。
3-2-1.在席確認のルールの取り決め
|
・POINT 始業・終業時間の連絡方法と同様、在席確認の方法についても、労使でルール化する。 |
在席確認の方法としては、様々な専用の労務管理ツールがあり、中には(不鮮明な状態の)労働者のデスクトップの画面を閲覧できるものもあるようです。そのようなツールを使って、業務を行っているかを確認するのでもよいと思いますし、電話にいつでも出られる状態にしておいたり、始業・就業のタイミングのほかに休憩明けの時間帯に報告のメールを送るなどの方法もあると思います。労使間でどのような方法で在席確認を行うかを協議して、ルール化するのが良いと思います。
3-2-2.私用の時間の取り扱い
私用の時間を認める場合、以下の二種類の方法が考えられます。
・私用の時間を休憩時間として取り扱う。
→ この場合、本来の休憩時間とは別にさらに休憩時間を取得することになります。在宅でのテレワークであれば通勤時間が無くなりますので、労働者との協議により、始業時刻を繰り上げたり、終業時刻を繰り下げるなどして本来の労働時間の確保を行うという方法が考えられます。始業・終業時刻の調整を行わなければ、ノーワーク・ノーペイの原則から休憩時間分の給与は発生しないことになりますが、労働者のニーズとはマッチしないでしょうから、私用の時間の取り決めを行うのであれば始業・終業時刻の調整はセットで対応する必要が出てくると思います。
この場合、始業・終業時刻を変更することになりますので、その旨を就業規則に記載する必要があります(労基法89条1号、労基法施行規則第5条1項2号)。
・私用の時間を休憩時間ではなく、時間単位の年次有給休暇として扱う。
→ 私用の時間を時間単位の年次有給休暇として扱いますので、休憩時間として取り扱う場合とは異なり、始業・終業時刻の調整は不要となります。
|
・POINT 業務時間内の私用の時間を認めるか否か、認めるとしてその時間をどのように扱うかについて取り決める必要がある。 私用の時間を休憩時間とするのであれば就業規則の変更が、時間単位の年次有給休暇として扱うのであれば、労使協定を締結させる必要がある。 |
この場合、労使協定の締結が必要となります(労基法39条4項)。
3-2-3.休憩の取り扱い
テレワークを導入した場合、休憩の取り扱いについても配慮する必要があります。
会社に出勤している場合、皆さんが同じ時間帯に昼休みを採る会社も多いと思います。これは、労基法で原則として休憩時間は一斉に与えなければならないと定められているからです(労基法34条2項)。
|
・POINT テレワークを導入する場合、休憩の取り扱いについて、労使協定で労基法34条2項を適用除外にする必要がある。 |
テレワークを導入する場合、休憩時間は各労働者まちまちになりますので、労使協定により34条2項を適用除外にする必要があります。
3-2-4.事業場外みなし労働時間制
以上のように、テレワークを導入した場合、出社して業務を行うという従来型の働き方とは異なり、使用者は労働者の労働時間の把握が困難になるため、以上で見たような様々な取り決めをする必要があります。
そこで、事業場外みなし労働時間制を利用して、一定時間を労働時間であるとみなすという取り扱いをする方法もあり得ます。
|
労基法第38条の2第1項 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 |
では、事業場外みなし労働時間制とはどのような制度でしょうか。まず、条文を見てみたいと思います。
事業場外みなし労働時間制とは、労働者の具体的な指揮監督下にない状況で労務を行った場合の労働時間の取り扱いに関する規定です。テレワークにおいても、使用者が労働者の「労働時間を算定し難い」場合には、所定労働時間労働したものとみなします。また、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を労働時間とみなすことができることになります。
では、テレワークを導入する場合に、どのような場合に事業場外みなし労働時間制を利用できるのでしょうか。
・要件1
テレワークが、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
・要件2
テレワークで使用しているパソコンが、使用者の指示によって常時通信可能な状態となっていないこと
→ 例えば、回線が接続されているだけで、労働者が自由に情報通信機器から離れることや通信可能な状態を切断することが認められる場合、会社支給の携帯電話等を所持していても、労働者の即応の義務が課されていないことが明らかな場合などが該当します。
・要件3
テレワークが随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
→ ここでいう「随時使用者の具体的な指示に基づいて行われる」に、テレワークの目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、これらの基本的事項について変更を指示することは含まれません。
以上の要件を満たす場合には、「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難」といえ、事業場外みなし労働時間制を採用できます。
なお、その場合、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」の時間数については、労使間の労働協約で定めることになります(労基法38条の2第2項)。
|
・POINT 要件をすべて満たす場合には、労働協約にて「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を決める必要がある。 |
4.業務の進捗状況の把握
使用者にとって、労働者の業務の進捗状況が分かりにくくなるというのも、テレワークの特徴です。しかし、業務の進捗状況が分からなければ、ある労働者が仕事を抱え込みすぎて納期に間に合わなかったり、心身の健康に支障をきたす場合もあります。また、労働者間の業務量の均衡が図れず、不公平感が生じる可能性もありますし、業務を分散させることで割増賃金の発生を抑制することにもつながります。
そこで、労働時間の把握とともに、業務の進捗状況の把握も、使用者にとっては重要となってきます。
|
・POINT 業務の進捗についての連絡の頻度、内容について労使でルール作りをする必要がある。 |
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
- 労務問題
- 弁護士による景品表示法(景表法)
- 優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説
- 消費者庁からの措置命令とは?措置命令を受けたときにすべきことを弁護士が解説
- 景品表示法に違反する「おとり広告」とは?具体例と罰則について弁護士が解説
- eスポーツと景品表示法
- キャッシュバックをする際の注意点を景表法に強い弁護士が解説
- アフィリエイト広告において気を付けるべき景表法ポイント
- この広告は景表法違反?弁護士による最近の景表法の違反事例解説
- 「PR」表記は必要?ステマにならない広告の出し方を弁護士が解説
- 期間限定の表示は誤認となる?景表法に強い弁護士が解説
- 展示会などでアンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡す際に景品の金額に規制はあるのか?
- ステマ広告への新たな規制について弁護士が解説
- 短尺でも要注意!動画広告が景表法違反となるケースと対策を弁護士が解説
- 求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説
- 「顧客満足度99%」「業界No.1」などの広告は危険?景表法上の問題について弁護士が解説
- 実演シーンを使った動画広告に潜む景表法違反ポイントを弁護士が解説
- 通信販売業の景表法ポイントを弁護士が解説
- PR表示だけでは不十分?SNS広告で問題になる景表法リスクを弁護士が解説
- 景品類の認定と取引付随性
- 二重価格表示にあたるケースについて解説
- 広告審査サポートは弁護士にお任せください。
- 景表法に関係するガイドラインについて弁護士が解説
- 打消し表示について弁護士が解説
- コンプガチャの景表法上の問題について
- 生成AIで作成されたコンテンツに関する法的問題について弁護士が解説
- 「好評につき延長」を使いたい!キャンペーン期間の延長に景表法の問題が無いか弁護士が解説
- 不当表示に関するよくあるご質問
- 景品規制に関するよくあるご質問
- 二重価格表示のルールについて解説
- このクーポンは大丈夫?景表法の規制を受けるクーポンについて
- 広告宣伝・景品表示法に関する 弁護士による法律相談
- コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか弁護士が解説
- 薬機法とは?規制概要や薬事法との違い、違反した場合の罰則について弁護士が解説
- 商標・特許
- 著作権
- 学校法人の法律問題
- 建物の明渡し
- 民事保全事件
- 債権回収
- 契約書
- 事業承継
- 破産・会社整理・特別清算
- 税務問題
- 不祥事対応
-
お知らせ2026/01/22
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16
-
弁護士コラム2025/11/26
-
お知らせ2025/11/25