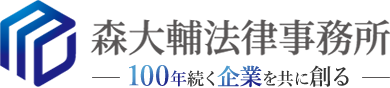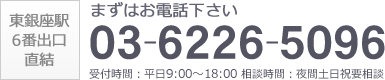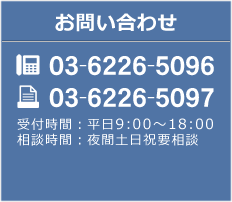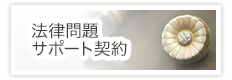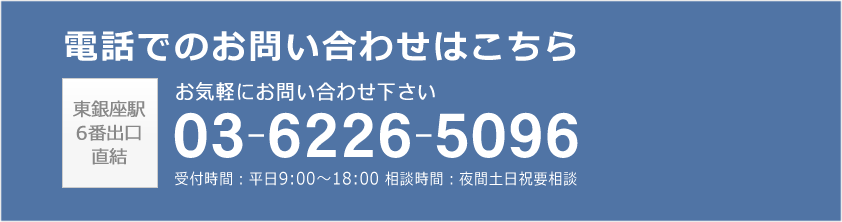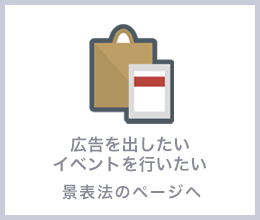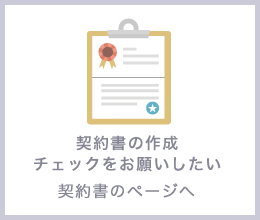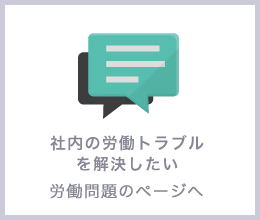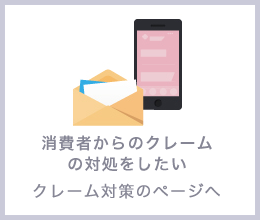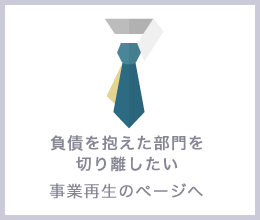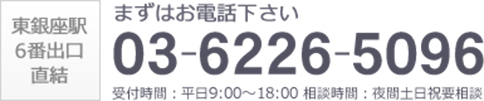薬機法に違反しない医薬品広告の作り方を弁護士が解説
![]()

Contents
1薬機法を遵守する重要性
(1)「薬機法」とは
日本における医薬品広告は、主に「薬機法」が規制しています。
「薬機法」の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
長年「薬事法」という名称で呼ばれておりましたが、2014年(平成26年)の法改正で「医療機器」が加わったことによって名称も「薬機法」に変更となりました。
(2)薬機法による医薬品広告規制の概要
(ア)虚偽・誇大広告の禁止
医薬品の名称、製造方法、効能・効果に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な広告をすることが禁止されています。
医薬品の効能・効果について、医師等がこれを保証したものと誤解されるおそれのある広告、堕胎を暗示した広告、わいせつな文書・図画を用いた広告も禁止されています。
(イ)特定疾病用の医薬品広告の制限
がんや白血病等の疾病に使用されることが目的の医薬品で、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものは、一般人を対象とする広告方法について制限されています。
(ウ)未承認医薬品の広告禁止
承認を受けていない医薬品について、その名称、製造方法、効能・効果に関する広告をすることは禁止されています。
(3)違法な医薬品広告を出した場合はペナルティ
(ア)違反広告に係る措置命令等
薬機法が禁止している虚偽・誇大広告をした者や未承認医薬品の広告をした者は、厚生労働大臣または都道府県知事から、その行為の中止、さらには、再発防止措置をとるように命令されます。
(イ)課徴金納付命令
さらに、虚偽・誇大広告をした者については、その医薬品の対価合計額の4.5%に相当する額の課徴金を国庫に納付するよう命じられてしまいます。
(ウ)刑罰
薬機法が規制している誇大広告等をした者は、拘禁刑(懲役)や罰金刑といった刑罰の対象となります。
(4)まとめ
このような薬機法による医薬品広告の規制は、消費者に対して正確で適切な医薬品情報を提供して、消費者の健康と安全を守り、信頼性のある医療環境を構築するためになされています。
そのため、違法な医薬品広告を出した者のペナルティも大きいものとなっています。
したがって、消費者のためにも自分自身のためにも、薬機法を遵守することは重要です。
2ガイドラインも重要
(1)ガイドラインとは
さらに、医薬品広告については、厚生労働省の定めた基準(「医薬品等適正広告基準」いわゆるガイドライン)に従って、広告が虚偽、誇大にわたらないようにすると共に適正なものにすることが求められています。
(2)ガイドラインにおけるNG例
(ア)広告表現全般
・ふざけたもの、嫌悪感を与えるもの、性的表現等で医薬品の信用を損なうもの
・アニメーションを用いる場合で、あまりにも誇張されたもの、品位に欠けるもの、視聴者に不快感・嫌悪感などを与えるもの
(イ)医薬品の名称におけるNG例
・他のものと同一性を誤認させるもの
・医薬品の愛称
(ウ)医薬品の製造方法を記載する場合のNG例
・「最高の技術」「最先端の製造方法」など最大級の表現
・「近代科学の粋を集めた製造方法」「理想的な製造方法」「家伝の秘法により作られた・・・」など最大級の表現に類する表現
・特許に関する虚偽・誇大な表現
(エ)医薬品の効能・効果についてのNG例
・承認等を要する医薬品について、承認等を受けた効能効果以外の効能・効果
・未承認の効能・効果についての表現のNG例(薬理学的に当該医薬品の作用と関係あるものでも、薬理学的に当該医薬品の作用と認められないものであってもNGな例)
・効能効果の二次的、三次的効果などの表現
・効能効果のしばり表現の省略・不正確な表現
・「食欲増進剤」
・「胃腸病の専門薬」「皮膚病の専門薬」(承認を受けた名称であればOK)
(オ)医薬品の成分を記載する場合のNG例
・有効成分が男性ホルモンであるものを「両性ホルモン」であると表現
・「高貴薬配合」「デラックス処方」
・「各種ビタミンを配合した・・・」「数種のアミノ酸配合・・・」
・「天然成分を配合しているので副作用がない」
・製剤自体が漢方製剤でないものについて「漢方処方の『●●エキス』に西洋薬を配合」
(カ)医薬品の用法容量を記載する場合のNG例
・承認等を要する医薬品について、承認などを受けた範囲を超えた表現
・承認等を要しない医薬品について、医学・薬学上認められている範囲を超えた表現
・「小児専門薬」「婦人専門薬」(承認を受けた名称であればOK)
・「いくら飲んでも副作用がない」
(キ)医薬品の効能効果や安全性を保証する表現についてのNG例
・「根治」「全快する」
・「安全性は確認済み」「副作用の心配はない」「刺激が少ない」「比較的安心して・・・」
・「●●(商品名)は▲▲年の歴史を持っているからよく効くのです」
・臨床データや実験例の例示(消費者に対して説明不足となり誤解を与えるおそれがある場合)
・承認外の効能効果を想起させたり、効果持続時間や安全性の保証表現となる図画・写真
・目薬、外皮用剤の広告で使用感のみを特に強調する表現
・キャッチフレーズなど強調表現として「優れたききめ」「よく効きます」
(ク)医薬品の効能効果や安全性についての最大限の表現をする場合のNG例
・「最高のききめ」「無類のききめ「肝臓薬の王様」「胃腸薬のエース」
・「世界一を誇る■■社の●●」「売上げNO.1」
・「比類なき安全性」「絶対安全」
(ケ)効能効果の発現程度についての表現のNG例
・単に「速く効く」
・「新幹線の大阪で痛んで京都で治っている」
(コ)本来の効能効果と認められない表現はNG
・頭痛薬について「受験合格」
・ホルモン剤について「夜を楽しむ」
・保健薬について「迫力を生む」「活力を生み出す」「人生を2倍楽しむ」
(サ)医師等の治療によらなけらば治癒が期待できない疾病名の記載はNG
・「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」「糖尿病」
・「高血圧」「低血圧」
・「心臓病」「肝炎」「白内障」「性病」
(シ)他社製品の誹謗はNG
・他社の製品の品質等について実際より悪く表現
・他者の製品の内容について事実を表現「どこでもまだ××式製造方法です」
(ス)不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告はNG
・「あなたにこんな症状はありませんか、あなたはすでに●●病です」
・「胸やけ、胃痛は肝臓が衰えているからです」
3医薬品広告の作り方
(1)医薬品「広告」に該当することを確認
(ア)医薬品広告の監督官庁である厚生労働省は、「薬事法における医薬品などの広告の該当性について」という通知において、以下の3要件すべてを満たす場合、「広告」に該当するものと判断し、監視指導の対象としています。
①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
②特定医薬品の商品名が明らかにされていること
③一般人が認知できる状態であること
(イ)したがって、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどの従来の広告媒体における広告に限られず、インターネット上のウェブ広告やSNS広告であっても、この3要件を満たす場合は「医薬品広告」として規制対象となります。
また、医薬品を個人輸入する場面に介在する輸入代行業者が、広告の中で医薬品について取り扱う場合であっても、この3要件を満たす場合は「医薬品広告」として規制対象となります。
(2)薬機法・ガイドラインをチェック
「医薬品広告」に該当する場合は、上記のような薬機法やガイドラインの規制に抵触しないように作ることが重要です。
まずはクリエイター御自身が薬機法等について学び、そのルールの範囲内で「医薬品広告」を制作することが必要です。
しかしそれでもクリエイターが「お客様に刺さる広告」を目指すがゆえに、客観的にみると薬機法に違反していると評価されてしまうこともあります。
薬機法による規制対象者は、広告主、広告代理店、広告を掲載した媒体(新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、WEBサイト)など幅広いため、大きな影響が及んでしまいます。
したがって、クリエイター以外の関係者にも、薬機法やガイドラインに抵触していないか自分事としてしっかり確認してもらうことが重要です。
会社内に企業法務に関する業務の担当者や法務部があるようでしたら、積極的にチェックしてもらうと良いでしょう。
(3)景品表示法など関連法規をチェック
(ア)関連法規をチェック
さらに、景品表示法など医薬品広告に関連する他の法規やガイドラインに違反していないかもチェックする必要があります。
たとえば、景表法に関係するガイドライン等です。
これについては、別記事 景表法に関係するガイドラインについて弁護士が解説 | 森大輔法律事務所 https://moridaisukelawoffices.com/page-67/page-346/page-3025
でわかりやすくまとめておりますので、ぜひご覧ください。
このような関連法規に抵触していないかについても、会社内に企業法務に関する業務の担当者や法務部があるようでしたら、あわせてチェックしてもらうと良いでしょう。
(イ)森大輔法律事務所に御相談ください
ただ、関連法規に抵触していないかも含めて幅広く医薬品広告をチェックするためには、幅広い法的知識と膨大な時間・労力が必要となり、大変な作業です。
その点、弁護士は、法律の専門家として、景表法、薬機法やガイドラインなど医薬品広告に関連する法規に幅広く精通していますので、弁護士に相談するのも良い方法です。
森大輔法律事務所には、テレビ等メディアで景表法・薬機法関連事件のコメンテータ―を務める弁護士、顧問先はじめ各社の広告表現について相談経験のある弁護士、他士業向け景表法・薬機法セミナーで講師を務める弁護士など医薬品広告に関連する法律に精通した弁護士が多数所属しております。
別記事 広告審査サポートは弁護士にお任せください!
https://moridaisukelawoffices.com/page-67/page-346/page-3277
もぜひご覧ください。
・制作した医薬品広告が薬機法はじめ関連法規に抵触していないか弁護士にチェックしてほしい方
・社内に法務部がなく、医薬品広告を出すのに不安を抱えている方
・社内に法務担当者はいるものの広告チェックは時間と労力の負担が大きいので外注したい方
・自社の医薬品広告が薬機法はじめ関連法規に抵触していないか点検して安心したい方
お気軽に森大輔法律事務所へご相談ください。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
-
お知らせ2026/02/06
-
お知らせ2026/02/06
-
お知らせ2026/01/22
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16