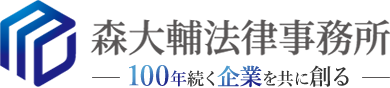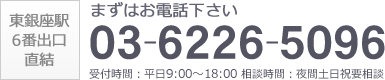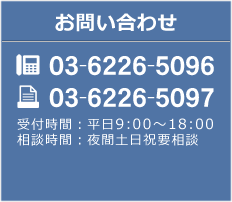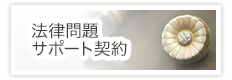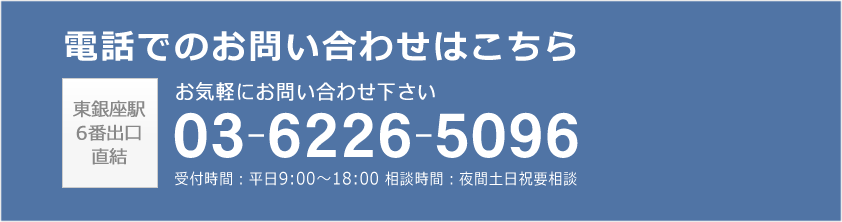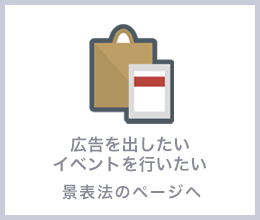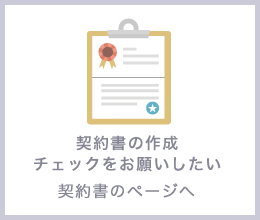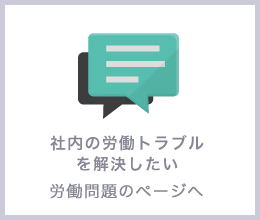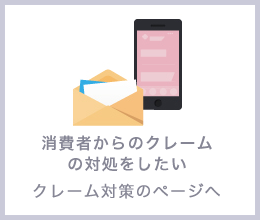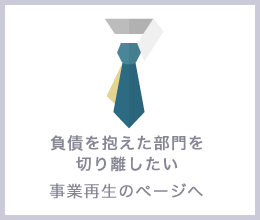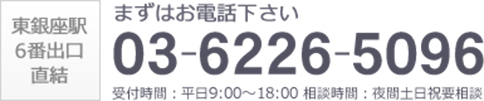薬機法における医薬品と医薬部外品の違いについて弁護士が解説

Contents
1はじめに
ドラッグストアに行って商品を手に取ったとき、パッケージに第●類医薬品と書かれたもの、医薬部外品と書かれたもの、両方をご覧になったことがあるのではないでしょうか。
実は、企業の製造・販売する商品が医薬品なのか医薬部外品なのかによって、広告で表現できる内容など、薬機法(正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)による規制が異なります。
そこで、ちょっと気になる医薬品と医薬部外品、その違いについて御説明いたします。
2医薬品と医薬部外品の定義
(1)薬機法の定め
医薬品等の品質・有効性および安全性の確保のために、薬機法が医薬品と医薬部外品について定義や規制を定めています。
(2)「医薬品」とは
(ア)定義
「医薬品」とは、
①日本薬局方に収められている物
②疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物であって機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)
③身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品および再生医療機器等製品を除く)
とされています。
(イ)詳しく説明
①「日本薬局方」とは医薬品の性状・品質の適正を図るために厚生労働大臣が公示した基準で約2000品目あり、ここに収載されている物は当然に医薬品となります。
②日本薬局方に収められている物以外は、その物の成分、形状、名称、その物に表示された使用目的・効能効果・用法用量、販売方法、その際の演述・宣伝などを総合して判断されます。
特に、
■医薬品的な効能効果を標ぼうするもの
■アンプル形状などもっぱら医薬品的形状であるもの
■用法用量が医薬品的であるもの
のいずれかに該当すると原則として医薬品とみなされます。
その結果、たとえ客観的に薬理作用を全く有さない物であっても、「医薬品」として薬機法の規制を受けて無承認・無許可の医薬品として指導・取締りの対象となってしまうので注意が必要です。
たとえば、インターネット上の無承認医薬品の広告に対しては、広告の中止等の指導が行われ、指導に従わない場合には広告中止命令をされることになります。
③治療や予防が目的でなくても、身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている物も医薬品です。
痩せる薬など健康な人が使用する場合も含まれ、医薬品該当性が②と同様に判断されます。
(ウ)医薬品の種類
医薬品は、大きく(A)医療用医薬品と(B)いわゆるOTC医薬品(Over The Counterカウンター越しに販売される医薬品)に分類されます。
(A)医療用医薬品
医師の処方に基づいて使用されることを目的として供給される医薬品です。
処方箋医薬品と、それ以外の医療医薬品に分けられます。
(B)OTC医薬品
薬局、ドラッグストア等の店舗販売業の許可を受けた者が販売できる医薬品です。
(a)要指導医薬品と(b)一般用医薬品に分類されます。
(a)要指導医薬品
インターネット等による販売(特定販売)ができず、薬剤師による対面販売を要する医薬品です。
(b)一般用医薬品は、副作用等による健康被害のおそれの程度に応じてリスクの高い順に、第一類、第二類、第三類に分類されます。
(3)「医薬部外品」とは
(ア)定義
これに対して「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいいます。
①次の目的のために使用されるものであって機械器具等でないもの
イ.吐きけその他の不快感または口臭・体臭の防止
ロ.あせも、ただれ等の防止
ハ.脱毛の防止、育毛または除毛
②保健のためにする、ねずみ、はえ、蚊、のみ、その他これらに類する生物の防除の目的で使用される物であって機械器具等でないもの
③本来であれば治療・予防等を目的としている「医薬品」の定義に当たる物のうち厚生労働大臣が指定するもの
とされています。
「人体に対する作用が緩和」とは、正常な使用方法において人体に強い作用を及ぼさないというだけでなく、通常予想される誤用の場合であっても作用が緩和であることを意味しています。
(イ)具体的な例
①口臭スプレー、デオドランド、制汗剤、育毛剤
②虫よけスプレー、殺虫剤、殺鼠剤
③健胃薬、整腸薬、消化薬、殺菌消毒薬、薬用化粧品、浴用剤
3医薬品と医薬部外品のちがい
(1)広告制作時に注意すべきガイドライン
医薬品も医薬部外品も、いずれも人の健康に深く関わるものなので、誤用、乱用等があった場合には健康被害の発生する恐れが大きいです。
そのため、他の製品以上に適正使用が強く求められ、製品に関する正確かつ適切な情報提供が不可欠です。
こうした観点から、医薬品、医薬部外品いずれも、薬機法における虚偽誇大広告禁止等の規定および医薬品等適正広告基準の適用を受け、不適切な広告が禁止されています。
(ア)医薬品
(A)医療用医薬品
医療用医薬品は、一般人が誤って使用した場合に健康被害リスクが高いので、医療関係者以外の一般人に対する広告がそもそも禁止されています。
そのため、医療用医薬品の広告の媒体・方法としては、医療関係者向けの新聞・雑誌、医療情報担当者(MR)による説明、文献・説明書等の印刷物等となります。
医療用医薬品の販売情報活動に関するガイドラインに注意が必要です。
(B)OTC医薬品
これに対して、OTC医薬品については、一般の消費者に対する広告が可能です。
そのため、適正広告基準と別に「OTC医薬品等の適正広告ガイドライン2019年版(OTC適正広告ガイドライン)」が定められているので、これにも抵触しないよう注意が必要です。
(イ)医薬部外品
医薬部外品についても、一般の消費者に対する広告が可能です。
そのため、医薬部外品の広告についても、OTC適正広告ガイドライン、さらに、化粧品等の適正広告ガイドラインの適用があるので、これらの業界自主ルールにも抵触しないよう注意が必要です。
(2)広告で「治る」と表現できるか
承認等を要する医薬品、医薬部外品のいずれにおいても、効能効果について広告する場合は、あくまでも承認を受けた効能効果の範囲を超えた表現をしないことが重要です。
また、承認等を要しない医薬品、医薬部外品の効能効果の表現についても、医学、薬学上認められている範囲を超えてはいけないことになっています。
(ア)医薬品
もっとも、医薬品は、疾病の診断、治療に使用される目的で人体に直接作用し高い有効性をもつものなので、「治る」という効能効果について承認を受けている等していれば、広告において「治る」という表現をすることが可能です。
(イ)医薬部外品
「治る」という表現は、疾病の治療すなわち医薬品的な効能効果を標ぼうするもので、医薬部外品としての承認等の範囲を超えることになります。
したがって、医薬部外品ではNGとなります。薬機法上の「医薬品」に該当し、無承認・無許可の医薬品として指導・取締りの対象となるおそれがあります。
ただ、有効成分が承認された効能効果を発現するための作用機序はOKです。
医薬部外品で表現できる効能効果の範囲については「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」として厚生労働省から示されているので、これを参考にするとよいでしょう。
4まとめ
このように薬局やドラッグストアでは同じように商品が並んでいるように見えますが、医薬品か医薬部外品かによって薬機法上の規制が異なっており、広告制作時に参考とすべき医薬品等適正広告規制の箇所やガイドライン、「治る」はじめ薬機法において許される広告の表現等が異なっています。
・医薬品、医薬部外品の広告の制作にとりかかる前に薬機法の疑問点を弁護士に質問してスッキリしたい方
・医薬部外品の広告案をつくったが、薬機法上OKか不安で弁護士に聞きたい方
・自社の医薬品や医薬部外品の広告において、薬機法上の問題がないか念のため弁護士に相談したい方
森大輔法律事務所では、複数の弁護士によるダブルチェックで親身に御対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
-
お知らせ2026/01/22
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16
-
弁護士コラム2025/11/26
-
お知らせ2025/11/25