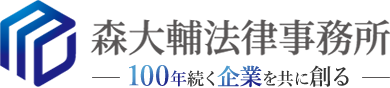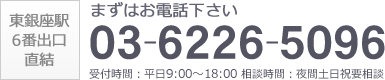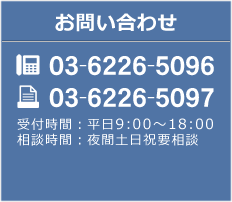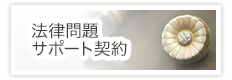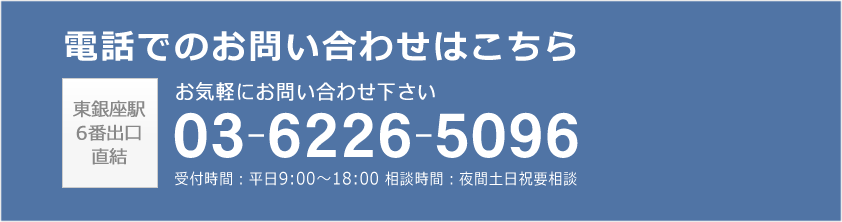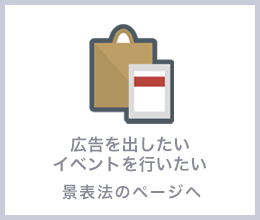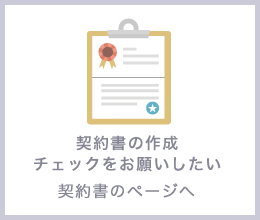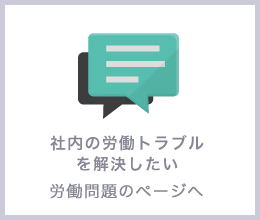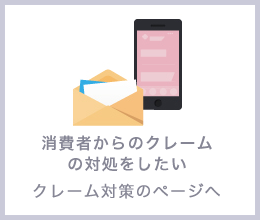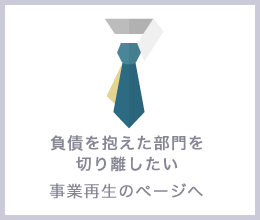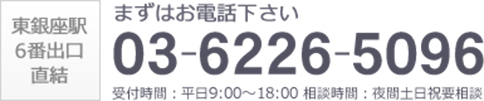民事訴訟による債権回収を行うメリットとは?
 企業活動において、売掛金の未回収や取引先の支払い遅延といった債権トラブルは、大小を問わず多くの企業にとって避けられない経営リスクの一つです。特に中小企業においては、1件の未回収債権が資金繰りに大きな影響を及ぼすこともあり、債権回収の手段とタイミングを適切に判断することが求められます。
企業活動において、売掛金の未回収や取引先の支払い遅延といった債権トラブルは、大小を問わず多くの企業にとって避けられない経営リスクの一つです。特に中小企業においては、1件の未回収債権が資金繰りに大きな影響を及ぼすこともあり、債権回収の手段とタイミングを適切に判断することが求められます。
債権回収には、内容証明郵便による催告、支払督促、民事調停、最終的には民事訴訟など、いくつかの選択肢があります。中でも「民事訴訟による債権回収」は、裁判所の判断に基づいて強制執行を可能にする手段として、法的な確実性が非常に高い回収方法です。
Contents
債権回収で民事訴訟を行うメリットとは?
強制執行による回収が可能になる
民事訴訟で勝訴判決を得ると、その判決書には債務者に対して一定の金額を支払うよう命じる内容が明記されます。この判決が確定すると、債務者が任意に支払いに応じない場合でも、債権者は裁判所に対して強制執行の申立てを行うことができます。強制執行の手続では、債務者の銀行口座、不動産、動産、さらには第三債務者に対する売掛金など、さまざまな資産に対して差押えを行うことが可能です。
例えば、ある取引先が約300万円の支払いを3か月以上滞納している場合、民事訴訟を提起し、勝訴判決を得ることで、債務者の保有する預金口座に差押えを実施できます。このように、実際に債権を現金化するためには、判決に基づく強制執行が最も確実な手段の一つです。
心理的プレッシャーを与えられる
債務者に対して訴訟を提起すること自体が、大きな心理的圧力となります。裁判所からの訴状送達を受け取った段階で、債務者は「法的なトラブルに発展した」と強く自覚し、任意の支払いに応じるケースが増加します。特に中小企業にとっては、訴訟対応による経営上の負担や社会的信用の低下を懸念する傾向が強いため、裁判を起こされた時点で交渉に応じる可能性が高くなります。場合によっては、第1回期日前に和解に至り、早期解決が実現することもあります。このように、民事訴訟は実際に判決を得ることが目的であるだけでなく、訴訟を通じた交渉促進ツールとしての機能も果たします。
時効の中断ができる
債権には消滅時効が存在し、一定期間が経過すると法的に請求できなくなる可能性があります。商取引における債権の多くは5年間の時効期間が設けられており、この期間内に訴訟を提起することで、時効が中断されます。つまり、時効の完成を防ぐことができ、再び新たに時効期間がスタートすることになります。
交渉材料として有効
債権回収における交渉の場面では、「法的措置を取る用意がある」という姿勢を明確に示すことで、相手方に対する交渉力が格段に向上します。実際に訴訟を提起することで、債務者側も無視や曖昧な態度を取ることが難しくなり、現実的な返済条件を提示してくる可能性が高くなります。例えば、請求額のうち一部を即時に支払い、残額を分割払いで返済するというような和解案が提示されるケースがあります。こうした状況では、訴訟手続を続行するか、和解によって回収スピードを優先するかの判断が求められます。民事訴訟は、企業にとって交渉戦略を柔軟に展開するための有効な選択肢です。
債権回収で民事訴訟を行うデメリットとは?
費用と時間がかかる
民事訴訟を提起するには、訴訟費用として印紙代や予納郵券が必要です。例えば、請求金額が100万円の場合、訴訟印紙代は1万円、予納郵券は裁判所によって異なりますが概ね6,000円から8,000円程度です。さらに弁護士に依頼する場合、着手金として10万円から30万円、成功報酬として回収額の10%から20%程度が相場となっています。また、訴訟の期間も考慮が必要です。簡易裁判所での少額訴訟であれば数か月で解決することもありますが、通常の民事訴訟では第1審だけでも6か月から1年程度を要することが一般的です。控訴があれば、さらに時間がかかることもあります。このように、訴訟には金銭的・時間的コストが伴うため、訴訟提起の判断には回収見込みと天秤にかけた上での慎重な判断が求められます。
相手の資力がなければ実質的な回収は困難
裁判に勝訴したとしても、債務者に回収可能な資産がなければ、実質的な回収は困難です。したがって、債務者がすでに資産を第三者に名義変更している、またはそもそも回収できる預金や不動産を保有していない場合、差押えを行っても現実的な回収は期待できません。このようなケースを避けるためには、訴訟提起前に相手方の資産状況や財務内容をできる限り調査しておくことが重要です。代表的な調査方法としては、不動産登記簿の取得、信用調査会社のレポート、過去の取引履歴の確認などが挙げられます。訴訟はあくまで手段であり、実効性のある回収に至るかどうかの見極めが重要となります。
関係性の悪化につながる可能性
民事訴訟は、法的トラブルを公式な形で解決するための手段であり、相手方との関係性に大きな影響を与える可能性があります。とくに長期的な取引関係がある取引先や、業界内での関係性が重要な場合には、訴訟によって今後の協力関係が破綻するリスクが高まります。
また、訴訟提起が業界内や取引先間で知られることにより、自社のイメージや信用に影響を及ぼす場合も考えられます。したがって、民事訴訟を選択する際には、その法的な効果のみならず、ビジネス上の影響や将来的な関係性についても十分に検討する必要があります。場合によっては、調停やADR(裁判外紛争解決手続)などの他の手段を先に活用する選択肢も視野に入れる必要があります。
債権回収のための訴訟手続の流れ
訴訟前の交渉・催告
訴訟に入る前に、まずは任意の交渉や催告を行うことが一般的です。内容証明郵便を活用して債務者に対して正式な請求書を送付し、一定の支払期限を設定します。この段階で支払いがあれば、訴訟に発展せずに債権回収が完了する可能性があります。また、この催告行為は後の訴訟において債権の存在と回収努力の証拠として活用できるため、記録は保管しておく必要があります。
訴状の作成と提出
債務者が催告にも応じない場合、訴訟提起を検討します。訴訟を起こすには、債権者が「訴状」を作成し、管轄の裁判所に提出します。訴状には請求の趣旨(「○○円を支払え」等)と、その原因(契約内容、支払期日、滞納状況など)を具体的に記載します。また、契約書、請求書、納品書、支払催告書などの証拠書類も併せて提出する必要があります。訴状の内容が不十分だと補正を求められる場合もあるため、法律の専門家による確認が推奨されます。
第1回期日〜審理の進行
訴状が受理されると、裁判所は被告(債務者)に対して訴状を送達し、第1回の口頭弁論期日を指定します。期日には原告(債権者)またはその代理人(弁護士)が出廷し、被告からの答弁書の提出と併せて双方の主張を整理していきます。訴訟の進行状況によっては、複数回の期日が設定され、証人尋問や書証の提出などを通じて事実関係の確認が行われます。中には、裁判所から和解を勧められるケースもあり、その場で和解が成立すれば、正式な和解調書が作成され、判決と同等の効力を持つことになります。
判決の取得・確定
審理がすべて終了すると、裁判所は判決を言い渡します。判決は通常、書面で交付され、判決主文にて支払命令などが記載されます。当事者のいずれもが控訴しなければ、その判決は確定します。判決確定日を起点として、債権者は強制執行の申立てを行うことができるようになります。判決が確定する前に強制執行を行うことはできませんので、確定のタイミングには注意が必要です。
強制執行手続きの開始
判決が確定し、なおかつ債務者が任意に支払わない場合、債権者は裁判所に対して強制執行の申立てを行います。強制執行にはいくつかの種類があり、最も一般的なのが預金口座の差押えです。他にも、不動産執行、給与差押え、動産執行など、債務者が保有する財産に応じた回収手段が選択されます。例えば、銀行預金への差押えを行う場合には、銀行名、支店名、口座番号などの詳細な情報が必要となります。これらの情報は事前に調査しておくことが実務上のポイントとなります。強制執行は裁判所の命令に基づいて行われるため、相手方が拒否しても、強制的に資産を回収することが可能です。
債権回収でお困りの場合は森大輔法律事務所まで
債権回収において「民事訴訟」を選択することは、単なる法的対立の手段ではなく、企業の資金繰りを守り、財務の健全性を維持するための有効な経営判断の一つです。強制執行による実効性ある回収を図れる点や、交渉戦略としての有用性、時効の中断といった多角的なメリットを享受できる一方で、費用や時間、相手方との関係性といったデメリットも併せて慎重に考慮する必要があります。
したがって、債権回収を民事訴訟で進めるかどうかを判断するにあたっては、法的な選択肢を十分に理解した上で、実情に応じた最適な手段を選ぶことが重要です。特に、訴訟の提起から判決、強制執行に至るまでの各段階では、法律の専門家である弁護士の関与が、結果に大きな差を生むことがあります。
もし、債権回収に関して、分からないことやお困りごとがございましたら、まずは森大輔法律事務所までご相談ください。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
- 「弁護士が教える低評価の Google クチコミにオーナー返信をする際のポイント」の記事を追加しました。 - 2026年1月13日
- 「薬機法とは?規制概要や薬事法との違い、違反した場合の罰則について弁護士が解説」の記事を更新しました。 - 2026年1月8日
- 「労働基準監督署(労基署)に通報されたら会社はどうなる?企業がとるべき対応について弁護士が解説」の記事を追加しました。 - 2025年12月25日
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16
-
弁護士コラム2025/11/26
-
お知らせ2025/11/25
-
お知らせ2025/11/14