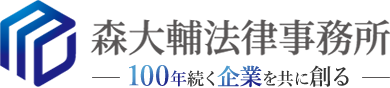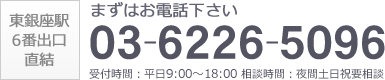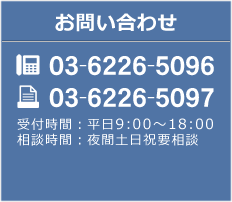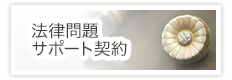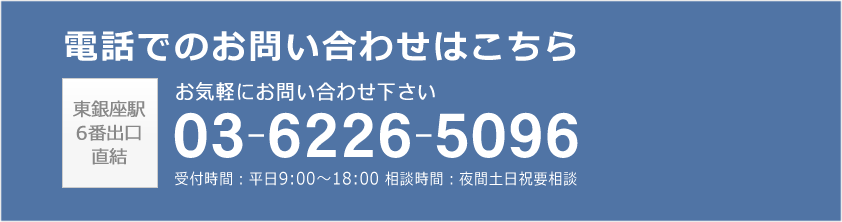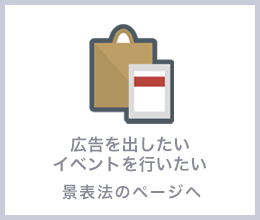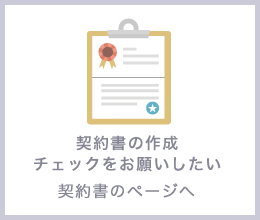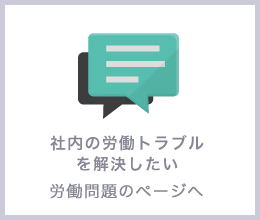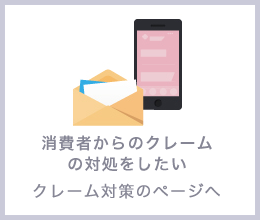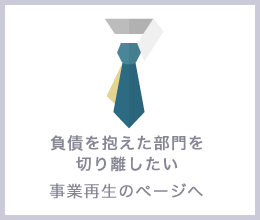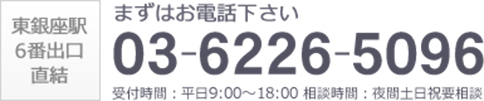Amazonセール(ブラックフライデー)における販売価格表示について

1 横行する見せかけの値引き販売
欲しかった商品をお買い得価格で購入できる人気のセール「Amazonブラックフライデー」が2025年12月1日まで開催されています。
盛り上がる一方で、一部の商品について「事前に価格をつり上げて、ブラックフライデーのセール期間中に値下げをすることによってお買い得に見せかけているのではないか?」という発言もネット上に散見されます。
Xの投稿などによると、Amazonに出品している一部の悪徳業者がブラックフライデーに便乗して、ブラックフライデーのセール開始前に販売価格を引き上げておいて、セール開始と同時に元の価格に戻すことによって、「◯◯%OFF」と大きな割引率を演出して、見せかけの値引価格で販売をしているケースがあるようです。
このような見せかけの値引きによる販売価格の表示は、景品表示法上の問題はないのでしょうか?
2 販売価格の表示に関する景品表示法の内容
(1)不当な販売価格の表示
販売価格の表示は、消費者にとって商品やサービスの選択をする上で最も重要な情報の一つです。
したがって、販売価格の表示が適正に行われない場合には、消費者の選択を誤らせることになってしまいます。
このような観点から、景品表示法は、事業者の販売価格について、消費者に実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認される表示(有利誤認表示)を不当表示として規制しています。
つまり、販売価格に関する表示については、次の2つの表示が景品表示法上、問題となります。
① 事業者が供給する商品やサービスの販売価格について、実際の販売価格よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示
② 事業者が供給する商品やサービスの販売価格について、競争事業者の販売価格よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示
(2)「著しく有利であると消費者に誤認される」とは
①②いずれであっても、有利であると消費者に誤認される表示が問題となります。
これは、当該表示により販売価格が真実と異なって「セールで安くなっていてお買い得♪」という印象を消費者に与えてしまうことをいいます。
「著しく有利」であると誤認される表示か否かは、その表示が、一般的に許容される誇張の程度を超えて、商品やサービスの選択に影響を与えるような内容か否かによって判断されることになります。
3 価格表示ガイドライン
(1)価格表示ガイドラインとは
消費者庁は、事業者による価格表示に関する違反行為を未然防いで適正な価格表示を推進するため、「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)を公表しています。
価格表示ガイドラインによって、監督官庁である消費者庁が具体的にどのような価格表示を消費者に誤認を与え景品表示法に違反するものと考えているのかを垣間見ることができます。
(2)過去の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示について
事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(比較対象価格)を併記して表示するものを、二重販売価格といいます。
二重販売価格は、その内容が適正な場合には、消費者がお買い得な商品を選択することや事業者間での健全な価格競争を促進に役立つ良い面もあります。
しかし、二重価格表示において、販売価格の安さを強調するために用いられた比較対象価格について適正な表示が行われていない場合、消費者に販売価格が安くてお得との誤認を与えることになってしまいます。
そのため、価格表示ガイドラインは、過去の販売価格と比較して安いとの印象を与える表示を行っているが、この過去の販売価格で販売した実績がない(又は不当に短い期間であった場合)比較に用いた販売価格が実際と異なっていて実際は安くない場合、景品表示法に違反する不当表示に該当するおそれがあると示しています。
4 見せかけの値引き販売
(1)不当表示に該当するおそれあり
Amazonブラックフライデーのセール開始前に販売価格を引き上げておいて、セール開始と同時に元の価格に戻すことによって「◯◯%OFF」と大きな割引率を演出して、見せかけの値引価格で販売をしているケースでは、ブラックフライデーのセール開始前という過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われています。
しかも、問題になるようなケースにおいては、比較対照価格がどのような価格であるか具体的に表示されていません。
このような場合、消費者は、通常、同一の商品がセール開始前の販売価格でセール前の相当期間ずっと販売されており、セール期間中だからこそ販売価格が値引き分だけ安くなっていてお買い得と誤認することになります。
したがって、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に、同一の商品について最近において相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、その価格がいつの時点でどの程度の期間実際に販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、あたかもセール期間の提供価格が通常提供している価格よりに比べて安いかのように消費者に対して示すことになります。
つまり、実際よりも有利であると偽って宣伝し、消費者に「セールで販売価格が安くなっていてお買い得♪」と取引条件についての誤解を与えることになるので、不当表示に該当するおそれがあります。
その結果、有利誤認表示を禁止している景品表示法に違反しているとして、消費者庁による取締の可能性があります。
(2)セール開催の決定後に販売を開始した場合
ちなみに、セール開催が決定された後に販売を開始した商品の二重価格表示については、商品の販売を開始する時点で、セールにて販売する価格か既に決まっています。
つまり、セール前の価格は実績作りのものとみられます。
そのため、たとえセール前価格で販売されていた期間を正確に表示していたとしても、不当表示に該当するおそれがあります。
したがって、やはり有利誤認表示を禁止している景品表示法に違反しているとして、消費者庁による取締の可能性があります。
5 景品表示法に違反した場合
(1)調査
景品表示法に違反する不当表示の疑いがある場合、監督官庁である消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。
(2)措置命令
調査の結果、違反行為が認められた場合、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対して、①不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、②再発防止策の実施、③今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。
違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は、「指導の措置」が採られます。
(3)課徴金納付命令
また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。
したがって、景品表示法に違反する不当表示の疑いを生じてしまうことは、事業者にとって、大きなリスクとなります。
6 弁護士の視点から対応策のアドバイス
このような事態に陥らないためにはどのように対応したら良いでしょうか?
一番は部署関係なく広告に携わる全従業員に向けた景品表示法の継続的な研修というのが一番有効であると考えます。
企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが重要です。
森大輔法律事務所においても、③社内教育の一環として、景品表示法の社内セミナーを担当することがありますが、法務部員だけの研修では意味がないと感じております。
なぜなら、広告に携わる従業員が問題意識をもって法務に相談しなければ意味がないからです。
研修を通じて、広告制作中に「あ、これは法務に相談すべき事項ではないか?」と気づき判断ができるようになることが一番の対策ではないかと思います。
森大輔法律事務所では、景品表示法に関する幅広いサービスを提供しております。
経験豊富な弁護士が個別の案件について親身になってご相談に応じております。
また、広告表示の適法性チェック、チェック体制のご提案、社内セミナーの開催についても幅広くご相談に応じております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
- 「薬機法とは?規制概要や薬事法との違い、違反した場合の罰則について弁護士が解説」の記事を更新しました。 - 2026年1月8日
- 「労働基準監督署(労基署)に通報されたら会社はどうなる?企業がとるべき対応について弁護士が解説」の記事を追加しました。 - 2025年12月25日
- 年末年始休業期間のお知らせ - 2025年12月24日
弁護士コラムの最新記事
- 英会話NOVA「入会金0円」キャンペーンの不当表示について
- ジャパネットたかたに対する措置命令の問題点について
- 島村楽器に対するフリーランス法違反の勧告について弁護士が解説
- 大正製薬に措置命令が。ステマ規制違反で注意すべきポイントとは?
- 学校法人がアカハラを弁護士に相談すべき理由とは|とるべき対策を徹底解説
- 【弁護士解説】カスハラ対策におけるポイントとは?
- 【保育園事業者向け】保護者からのクレームへの適切な対応方法
- 宝塚歌劇団の報道を受けて(不祥事対応とコンプライアンスの意識について)
- 病院やクリニックのクレームや苦情の初動対応のポイントとは
- 日本航空(JAL)の子会社の魅力的な景品提供はNG?
- クレベリン(大幸薬品)に対して過去最高額の課徴金納付命令がなされた件について弁護士が解説
- 悪質な誇大広告抑止のための景品表示法の改正案について
- 【弁護士が解説】「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」に対する措置命令事案
- 「求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説」の記事を作成しました
- 【弁護士が解説】インシップ「ノコギリヤシエキスサプリ」に対する広告の差止請求訴訟について
- 景品価値が異なる場合、懸賞?総付?
- スシロー「生ビール半額」広告の景表法問題について弁護士が解説
- 改正特定商取引法及び改正消費者契約法と景品表示法との関係性について
- 中村屋の入管法違反容疑について
- 大幸薬品に対する措置命令について
- ビックカメラへの措置命令について
- タイガー魔法瓶への措置命令について
- 株式会社ジャパネットたかたの不当表示について
- テレワークと労務管理
- タクシー会社ロイヤルリムジンの全社員600名解雇の問題点
- 新型コロナと労災
- 新型コロナウイルス感染拡大に伴う契約トラブルについて
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い従業員を休ませる場合の措置(主に休業手当について)
- 「電話かけ放題」の留意点
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16
-
弁護士コラム2025/11/26
-
お知らせ2025/11/25
-
お知らせ2025/11/14
-
お知らせ2025/11/12