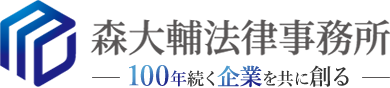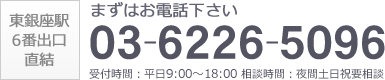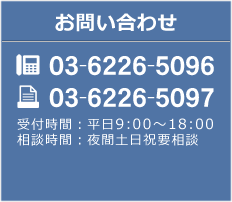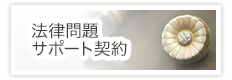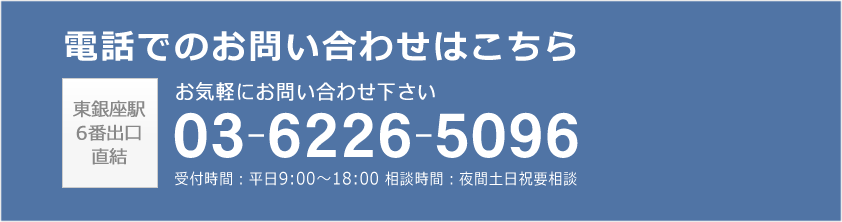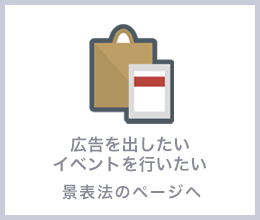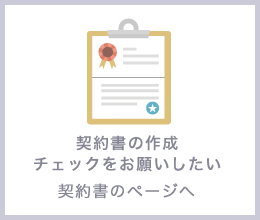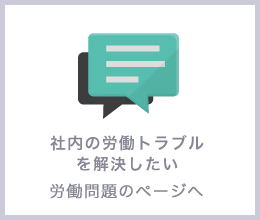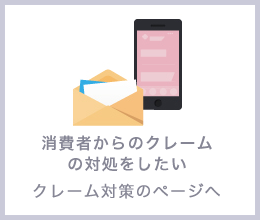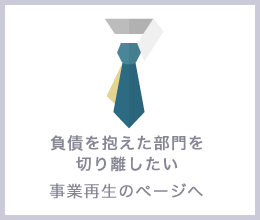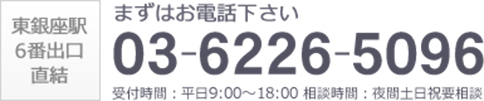教職員間でのハラスメントとは?発生例や対処法を弁護士が解説

近年、学校における教職員間のハラスメントを訴える事例がよく見られます。教職員の職場環境を守り、生徒が快適に学べる場所を作るためには、ハラスメントに対する学校側の適切な対応が欠かせません。そこで本記事では、教職員間で起こり得るハラスメントの特徴や、発生時の適切な対処方法について解説します。
Contents
学校法人における教職員間のハラスメントの実態
学校の職場において、教職員間で起こる可能性があるハラスメントには、以下のような種類があります。
- パワーハラスメント
- セクシュアルハラスメント
- マタニティハラスメント
- アカデミックハラスメント
学校の職場は人間関係が閉鎖的な傾向があるため、ハラスメント行為を認識しづらく、対処が遅れると被害が蔓延しやすいことが特徴です。被害を防ぐには、教職員間で発生しやすいハラスメントの特徴とその対処法を理解しておくことが重要です。
教職員間でのハラスメントがもたらす悪影響
教職員のモチベーション低下や離職
職場にハラスメントが発生すれば、教職員のやる気が低下し、離職のリスクが高まります。また、被害者だけでなく、周囲の人間にも強いストレスがかかることで、メンタルヘルス不調を引き起こす可能性もあるでしょう。
職場の雰囲気の悪化
教職員間でハラスメントが起こると、職場全体の雰囲気を悪化させる原因にもなります。「自分が次の被害に遭うかもしれない」という不安や「助けてあげられなかった」という罪悪感を周囲の教職員が抱くようになり、良好な職場環境を作ることは難しくなるでしょう。
生徒への悪影響
教職員間のトラブルは、生徒にまで悪影響を及ぼしかねません。教職員の精神状態が安定しない状態で、生徒が安心できる教育を行うことは難しいでしょう。離職や休職が発生した場合には、担任の変更などを行わなければならず、生徒に不安を与えることになります。
学校の評判の低下
教職員間のハラスメントは、学校の評判にも直結します。ハラスメントの発生が世間に知られれば、学校のイメージ低下や入学者の減少などにつながり、生徒や保護者からの信用を失う事態にもなりかねません。
教職員間で起こるハラスメントの具体例
では、実際にどのようなハラスメントが行われているのでしょうか。ここでは、その具体例を紹介します。
生徒の目の前での叱責
生徒が見ている場所で教職員を罵倒する行為は、ハラスメントに該当します。教職員にとって、生徒の前で評価を下げられる行為は、プライドを傷つけられるものであり、精神的苦痛を伴うからです。教職員に対して注意・指導をする際は、業務上必要な範囲に留め、生徒がいない場所で行う等の配慮が必要です。
行き過ぎた指導
職場における指導が一定の範囲を超えた過剰なものであれば、これもハラスメントに該当します。必要以上に厳しい指導は、過度なストレスを与えかねないからです。例えば、執拗に長時間指摘したり、大声で叱責することなどが該当します。指導の必要性が問われる線引きの判断は難しいですが、客観的に過剰であると判断され得る指導が行われている場合は注意が必要です。
教職員特有のハラスメント(アカハラ)
学校で起こり得る特有のハラスメントとして、アカハラ(アカデミックハラスメント)があります。アカハラとは、地位の高い教職員が教育・研究上の権力を濫用して、他の教職員や生徒に対して行う嫌がらせや不当な行為のことです。例えば、研究や教育の成果を横取りする、必要な指導をしない等が例として挙げられます。パワハラに括られることもありますが、学校という職場特有のハラスメントが起こり得ることを理解しておきましょう。
教職員間でハラスメントが起こった際の対処法
関係者への聞き取り調査による事実確認
教職員間でハラスメントが発生した場合、まずは聞き取り調査を行なって現状を確認する必要があります。事実確認にあたって、被害者の意見を親身に聞くことはもちろんのこと、加害者や周囲の人間など、さまざまな立場からの意見を聞き、客観性を意識しながら現状の確認を行うことが重要です。
適切な指導
ハラスメントが発生した場合、加害者の教職員には適切な注意・指導を行わなければなりません。再び同じ問題を起こさないように、行為の問題性と被害者の意見を理解させる必要があります。また、改善のために何をすべきかを本人に考えさせ、対応策を提示させることで、意識の改善を図ることも重要です。
懲戒処分
ハラスメントを行なった教職員に改善の様子が見られない場合、懲戒処分を検討することになります。懲戒処分をせずに放置すれば、学校側にも責任が発生するケースがあるので注意が必要です。ただし、懲戒処分は行為に対して妥当な処分でなければ、逆に訴えられるというリスクもあります。軽微な処分から開始し、改善がない場合は段階的に厳しい処分を検討しましょう。処分の決定には法的観点から専門的な判断が必要になるため、弁護士に相談することを推奨いたします。
再発防止策の策定と実施
教職員間でハラスメントを再び発生させないためには、再発防止策を策定して実施することが重要です。教職員に対して研修や啓発資料の配布を行い、職場全体でハラスメントへの理解を深める必要があります。また、相談窓口を設置したり、定期的にアンケートを行ったりすることで、ハラスメントの早期発見を行える体制を作ることも有効な方法です。
弁護士に相談するメリット
法的な観点からのアドバイス
教職員間のハラスメントについて弁護士に相談をすれば、法的な観点からアドバイスを受けることが可能です。ハラスメントに対処する過程では、ハラスメントの事実認定や処分の決定判断において、法律や過去の裁判例に基づく専門的な知識・経験が求められる場面が多くあります。自力で対処を進めると、対応が遅れて被害が拡大したり、判断を誤って処分の無効を訴えられたりする事態になりかねません。弁護士に相談をすれば、事情に応じた適切な対処を行うことが可能です。
問題が長期化・深刻化することを防ぐ
ハラスメント問題を弁護士に相談すると、紛争の長期化や深刻化を防ぐことができます。当事者双方の意見がぶつかり合った場合、事実認定や処分決定に対して紛争が起こりかねません。そうなった場合でも、弁護士に相談をすれば、穏便かつ迅速に解決を図ることが可能です。
再発防止のための体制構築
弁護士に相談をすれば、ハラスメントの再発防止のための体制構築についてもアドバイスをすることが可能です。再発防止のためには、法律や過去の事例に基づく必要があるため、弁護士の専門的な意見を取り入れることが重要です。
また、職場内で作成したものは客観性に欠けることもあるため、第三者に有効性を確認してもらうという点でも、弁護士に相談することは効果的です。
訴訟・示談対応
当事者間の紛争が深刻化したり、懲戒処分の無効性を訴えられたりした場合には、訴訟や示談の対応が必要になる場合があります。弁護士に相談をすれば、これらの対応を代理で行い、複雑な法的手続きを正確かつ迅速に進めることが可能です。これにより、紛争解決にかかる時間や労力を大幅に削減することができます。
教職員間でのハラスメントにお悩みの方は当事務所にご相談ください
教職員間のハラスメントは、職場環境や生徒に大きな悪影響を及ぼします。被害を拡大させないためには、教職員間で起こりやすいハラスメントの特徴を把握し、早期の発見と適切な対処を行うことが必要です。
当事務所では、職場の人事・労務問題の実績と経験が豊富な弁護士が、防止策の検討から紛争対応まで徹底してサポートいたします。教職員間のハラスメントにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
- 教職員間でのハラスメントとは?発生例や対処法を弁護士が解説
- 奨学金が滞納されているとき
- スクールロイヤーと顧問弁護士は何が違う?
- 教職員のメンタルヘルスを守るために学校側が知っておきたいポイントとは
- 修学旅行の引率をした教職員に支払うべき手当
- 教職員から未払い残業代請求をされた場合に学校法人がとるべき対応や請求の予防策を解説
- 学校法人の就業規則等の点検や改定
- 教職員への懲戒処分
- 生徒に対する懲戒処分
- 教職員への懲戒処分
- モンスターペアレント(モンペ)からのインターネット上での誹謗中傷に対する対応策!学校トラブルについて弁護士が解説
- 授業料・給食費の滞納
- 生徒への懲戒処分
- 学校事故が発生した際の対処策
- 学校法人における個人情報の管理
- モンスターペアレント対応
- いじめ防止対策推進法について
- 子供同士のけんかをいじめだとして学校に対応を求めてくる!弁護士が解説するモンスターペアレント(モンペ)対応
-
お知らせ2026/01/22
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16
-
弁護士コラム2025/11/26
-
お知らせ2025/11/25