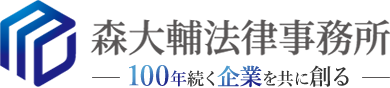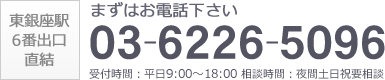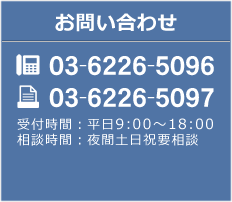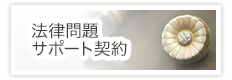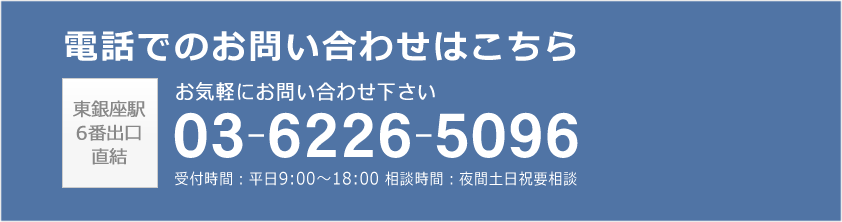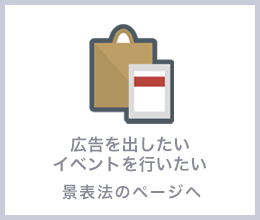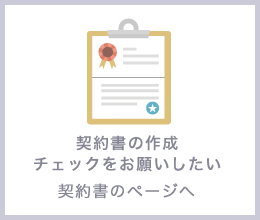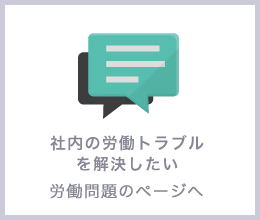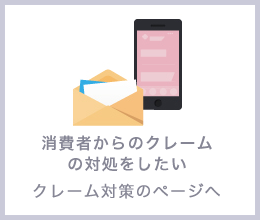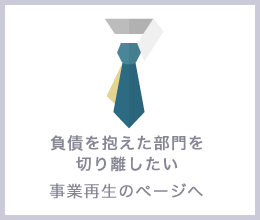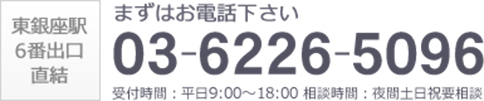従業員が社外秘や誹謗中傷などの不適切な投稿をしている際に出来る対応は?

Contents
1 従業員が社外秘を投稿している場合
従業員が、会社の広報担当としてFacebook、Instagram、Xなどの公式SNSで投稿することも増えていますが、それと同時に、個人のアカウントを持ちプライベートで投稿するケースも増えています。
その内容が従業員のプライベートの範疇にとどまっているかぎりは、会社に何らの影響もなく、会社の支配が及ぶものではありません。
しかし、従業員が社外秘の情報を勝手に投稿した場合、たとえ従業員個人の炎上であっても、投稿された情報が世間に拡散された結果、会社に損害を生じることがあります。
(1)未発表の新商品
たとえば、まだ未発表の新商品に関する情報が勝手に投稿された場合、競合他社がその情報を入手することによって、会社に莫大な経済的損失が生じます。
(2)個人情報
また、たとえば来店した芸能人の個人情報が勝手に投稿された場合、画像等から会社も特定され、この会社で個人情報が流出した事実が拡散されて、会社のブランド・イメージが悪化し社会的信用が失墜します。その結果、会社は、売上の減少、取引の中止、株価の下落、就職希望者の減少、離職者の増加などによる損害を被るリスクが高まります。
さらに、従業員による勝手な投稿であっても、会社は使用者責任(民法第715条)を問われて、投稿の被害者から、情報流出による損害の賠償を請求される可能性もあります。
2 従業員が会社への誹謗中傷を投稿している場合
たとえば「不良品ばかりを売っている詐欺集団」「ブラックだ」などと根拠のない誹謗中傷が投稿され拡散した場合も、会社や社長のイメージや信用が悪化して、売上の減少、取引の中止、株価の下落、就職希望者の減少、離職者の増加などによる損害を被るリスクが高まります。
3 不適切な投稿をしている従業員に会社ができること
このような損害を最低限にとどめるため、従業員による不適切な投稿を発見した場合、会社はスピーディーに対処することが重要です。
(1)投稿の削除を要請する
ア.投稿を保存する
SNSの投稿は、投稿者が簡単に編集・削除できてしまいます。
そのため、不適切な投稿があった証拠を記録しておくことが重要です。
たとえば、スクリーンショット、キャプチャ、紙にプリントアウト等して保存します。
イ.投稿者を特定する
実名アカウントでない場合は、投稿した従業員が誰なのかを特定する必要があります。
情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)第5条に基づくプラットフォーム事業者等に発信者情報を開示させるための裁判手続は、法律に沿った専門的な手続が必要なため、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
ウ.事実確認&削除要請
投稿した従業員に対して、事実を確認するため聞き取り調査を行います。
そして、できるだけ早く、投稿を削除するように要請します。会社の被害を最小限にとどめるためにも、削除要請は早い段階で行うことが重要です。
なお、従業員が削除要請に応じない場合は、サイト管理者に対して削除申請します。
削除申請が認められない場合は、投稿削除の仮処分(裁判手続)をすることになります。仮処分は、法律に沿った専門的な手続が必要なので、弁護士に依頼することをオススメします。
(2)懲戒処分
社外秘などの不適切なSNS投稿が、就業規則上、守秘義務違反などの懲戒事由に該当する場合、会社は従業員に対して懲戒処分を行うことができます。
ただ懲戒事由に該当する場合でも、悪質性や被害の程度等の事情に照らして重すぎる処分(たとえば懲戒解雇)は、後日、裁判において無効と判断される可能性があります(労働契約法第15条)。
したがって、どの程度の処分を行うかは、弁護士に相談しながら決定すると良いでしょう。
(3)損害賠償の請求
会社に損害を与えるような不適切投稿をした従業員に対して、損害賠償を請求をすることも可能です。
どの程度の金額を請求するか等について専門的な判断が必要になりますので、弁護士に相談することを推奨します。
(4)刑事告訴
「A社は不良品ばかり売っている詐欺集団」などと誹謗中傷する投稿によって会社の名誉を毀損した従業員を名誉毀損罪(刑法第230条)で刑事告訴して、刑事罰を求めることもできます。
4 会社が取り組むべきSNS管理
従業員による不適切な投稿の発端は、ささいな原因であることが多く、あらかじめ対策をしておけば未然に防げた事案も多くあるように思います。では、具体的に会社はどのようなSNS管理に取り組むべきでしょうか?
(1)就業規則などの整備
就業規則や誓約書を見直して、不適切投稿を禁止し違反すると懲戒事由になる条項を追加するなど、SNS投稿によるトラブルに対応できるようにします。
また「SNS利用についてのガイドライン」も整備します。SNSの使用法、投稿する際の注意点やリスクについて記載します。会社公式SNSに限らず、従業員個人のアカウントによるSNS投稿に関しても項目を設けると良いでしょう。
必要に応じて、弁護士によるリーガルチェックやアドバイスを受けることを推奨します。
(2)「内部通報制度」の整備
SNSは気軽に投稿できて拡散力があるところから、内部告発にも使われがちです。そこで、従業員が会社への不満を、SNS投稿によることなく、社内で相談を受けて解決策を講じ改善できる仕組み、すなわち「内部通報制度」の整備が必要です。
上司や同僚によるハラスメントなどコンプライアンスに反する不満や悩みやを気軽に相談できる窓口を設けて、すべての従業員に周知しておくとよいでしょう。
(3)コンプライアンス研修
従業員による不適切な投稿は「違法だとは知らなかった」や「ついうっかりやってしまった」など、SNS利用に関するガイドラインや就業規則を理解できていないことが1つの要因になっています。
そのため、会社のリスクを最小限に抑えるには、すべての従業員に対して、入社時のみならず定期的にSNS利用に関するコンプライアンス研修が効果的です。
「SNS利用についてのガイドライン」を研修資料として活用して、どのような情報を投稿すると、たとえ悪意のない投稿であっても法令違反になったり社外秘に該当してNGになるか、具体的に説明すると効果的です。
また、実際のSNS投稿で炎上した事例を取り上げて、不適切な投稿が会社のみならず顧客や取引先にまで悪影響を及ぼし会社にとって大きなリスクになることや、投稿者自身が法的責任を問われて損害賠償を請求されたり刑事告訴されて逮捕・裁判を受け得ることを自覚していただくと、従業員による不適切な投稿への抑止になります。
上司・同僚によるハラスメントや会社への不満を相談できる窓口が設置されている旨も、あわせて周知しておくと良いでしょう。
5 まずは弁護士にご相談ください
(1)リーガルチェックから裁判まですべて対応できます
昨今、SNS投稿による誹謗中傷や社外秘の漏洩は、会社にとって身近で深刻な問題になっています。
もたもたして対応に時間がかかってしまうと、不適切な投稿がどんどん拡散して損害が大きくなってしまうリスクがあります。
したがって、このような不適切投稿でお悩みの場合、速やかに弁護士に相談・依頼することをオススメします。
企業法務に精通した弁護士であれば、就業規則等のリーガルチェックや社内研修などによる事前の防止策の整備、トラブル発生時における投稿者の特定、投稿者への聞き取り、投稿の削除請求、懲戒処分の具体的検討、損害賠償請求の裁判、刑事告訴などオールマイティに対応できます。
(2)森大輔法律事務所は、誹謗中傷・風評被害対策に力を入れております
森大輔法律事務所は、企業法務をサポートする事務所としてスタートしましたが、企業がネット上で風評被害を受けることが増加した時代背景に合わせて、誹謗中傷・風評被害対策にも注力し、SNS投稿削除はじめネットトラブルの御相談や御依頼を10年間で数多くお受けしてきました。
ゆえに、就業規則や「SNS利用についてのガイドライン」等のリーガルチェック、社内でのコンプライアンス研修、懲戒処分の具体的検討、投稿者の特定、投稿した従業員への聞き取り、投稿の削除請求、損害賠償請求の裁判、刑事告訴などすべての法務に対してオールマイティに対応できます。
投稿の削除に成功した実績も多数ございます。
これまでのネットトラブル・誹謗中傷に関する御相談や解決事例の一部をホームページで解説しておりますので、ぜひご覧ください。
誹謗中傷対策・情報開示請求・風評被害対策 | 森大輔法律事務所
(3)24時間いつでも問い合わせOK!
森大輔法律事務所は、投稿削除の実績がある誹謗中傷に強い弁護士が、最適な方法でスピーディーに対応するので、SNS投稿に関するお悩みを大きく減らすことができます。
・誹謗中傷や社外秘の漏洩などの不適切投稿にどう対処すればよいか分からず悩んでいる方
・不適切投稿の削除を弁護士に任せて、無駄な労力・時間・ストレスから解放されたい方
・弁護士による就業規則や「SNS利用についてのガイドライン」のリーガルチェックやアドバイスが欲しい方
・「弁護士によるSNS利用に関するコンプライアンス研修」を受講・開催したい方
・日常の法律相談やリーガルチェックでトラブルを未然に防止でき、さらに不適切投稿などのトラブルにもスピーディーかつ親身に善処してくれる顧問弁護士がほしい方
森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでも相談できます。
【相談はこちら】
誹謗中傷対策の経験豊富な弁護士が喜んで対応いたします。
女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。
オンラインWeb会議ツール(ZOOM)を活用して、全国どこでも対応できます。
現にトラブルが起きている、事前の防止策を整えたいなど、お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
- Googleクチコミや転職サイトに悪質な書き込みをされた!投稿者の特定やクチコミの削除のためにまずするべきこと
- 病院・クリニック・歯科医院で多いGoogle口コミトラブル!口コミ削除を弁護士が解説
- 問題社員が、ネットに「ブラック企業」など会社の悪口を書き込んでいる!削除や対応方法を弁護士が解説!
- OpenWork でのクチコミに対処するには?削除や開示の方法を弁護士が解説
- Google口コミの削除をしたい!書き込み削除を弁護士に相談
- Googleの悪い口コミは営業妨害になる?弁護士が解説
- 転職会議の書き込みを消したい !削除の方法を弁護士が解説
- 従業員が社外秘や誹謗中傷などの不適切な投稿をしている際に出来る対応は?
- 【2025年4月施行】情報流通プラットフォーム対処法について弁護士が解説
- Yahoo!ファイナンス掲示板へのコメント(誹謗中傷)の削除をする方法を弁護士が解説
- 企業への誹謗中傷を削除したい!サイト別の口コミを削除する方法を弁護士が解説
- 発信者情報開示請求とは?口コミ投稿者を特定する方法を弁護士が解説
- 削除できる誹謗中傷とは?代表的な「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」とは?弁護士が解説
- YouTube で会社への誹謗中傷を削除できる?自社のブランドを回復する方法とは
- Google 口コミを削除したら投稿者に通知が行ってバレる?誹謗中傷削除に詳しい弁護士が解説
- クチコミの削除は誰に相談する?非弁行為と削除費用
- OpenWorkに「社長のトップダウン」「社長に気に入られる必要がある」を書かれたらクチコミ削除できる?弁護士が解説
- このクチコミは名誉毀損?Googleクチコミが名誉毀損になるケースを弁護士が解説
- 弁護士が教える低評価の Google クチコミにオーナー返信をする際のポイント
-
お知らせ2026/02/06
-
お知らせ2026/02/06
-
お知らせ2026/01/22
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16