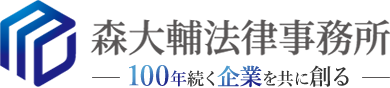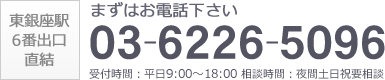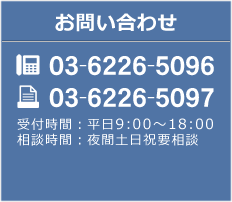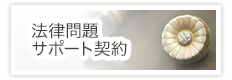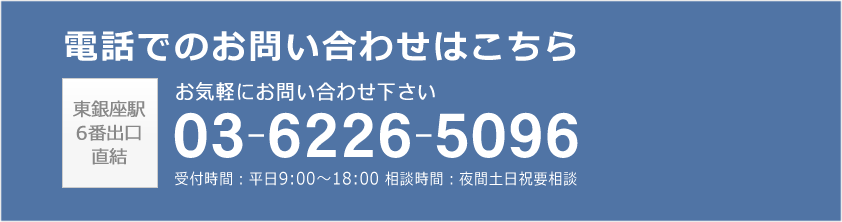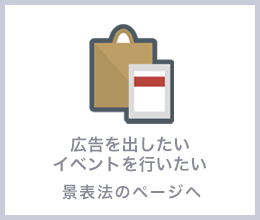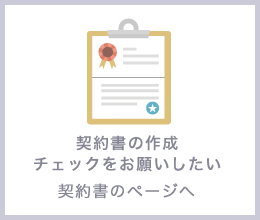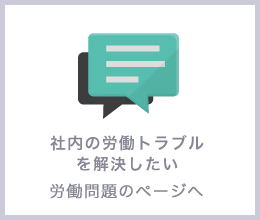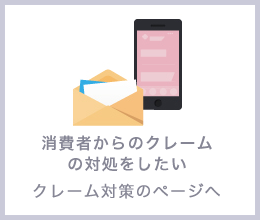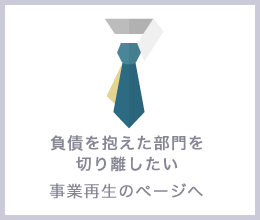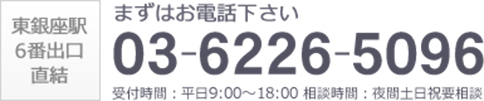健康食品の広告表現における薬機法の注意点を弁護士が解説

Contents
(1) 健康食品と薬機法についての基礎知識
① 薬機法とは何か
商品パッケージ、チラシ、アフィリエイトなど健康食品のあらゆる広告においては、薬機法に違反しないように注意する必要があります。
薬機法とは、医薬品等の品質、有効性、安全性を確保し、国民の健康への危害を防ぐための法律です。
詳細につきましては、「薬機法(旧薬事法)について弁護士が解説」の記事でわかりやすく解説しておりますので、こちらをご覧ください。
薬機法は「医薬品」「医療部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の5分野からなっており、健康食品については直接的に規制していません。
しかし、健康食品に関する広告表現が薬機法が規制する領域に入り込むと薬機法違反になります。
そのため、薬機法の領域に入り込むとは具体的にどういうことで、どのような表現がNGか、どのように言い換えればOKか、わかりづらくなっており悩まれる方も多いようです。
そこで、健康食品の広告表現における薬機法の注意点を弁護士がわかりやすく解説します。
② 健康食品の定義と分類
いわゆる「健康食品」とは、サプリメントなど健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂取される食品全般をいいます。
健康食品のうち後述の保健機能食品でないものは、通常の食品(一般食品)です。
一般食品においては、食品の持つ効果や機能を表示することができません。
単に健康の維持や増進を目的として健康を補助したり、栄養を補助・調整したりする食品として、健康補助食品、栄養補助食品、栄養調整食品といった表示で販売されています。
(2) 健康食品の広告表現における言い換えポイント
① 違反表現と言い換えポイント
もし健康食品の広告で疾病の治療・予防に使用されることが目的の食品であると誤認される表現をしてしまうと、薬機法上の「医薬品」に該当することになってしまいます。
しかし「医薬品」として国の承認を受けていないため、承認前医薬品の広告に該当し、薬機法68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に違反します。
例えば、飲む時期、飲む量、飲み方など用法・用量を指定したり、医薬品専用の成分と同じような効果が得られるかのような表現をすると、「医薬品」に該当してNGとなります。
このような違反表現は、目安量、摂取上限、推奨するお召し上がり方や作り方等によって言い換えることがポイントです。
【具体例】
・「1回1錠、毎日3粒」
=用法・用量が医薬品的に指定され、医薬品と誤認される違反表現なのでNG
→「1日摂取目安量1~3粒」と目安量として言い換えOK
「1日5粒を上限にお飲みください」と推奨する飲み方・摂取上限として言い換えOK
② 効果効能の表現における注意点
特に注意が必要なのは、健康食品の効果効能についての広告表現です。
健康食品において、医薬品的な効果効能を広告に記載してしまうと薬機法上の「医薬品」と認定されて薬機法違反になるので注意しなくてはなりません。
疾病の治療・予防になるかのような表現はNGです。
【具体例】
・「糖尿病改善、抗がん作用、感染症予防に効きめ抜群」としてサプリメントを販売
=疾病の治療・予防が目的の「医薬品」に該当するためNG
また、後述の保健機能食品ではない健康食品(一般食品)については、食品の機能を表示することもできません。食品の機能を示す表現もNGです。
これらの場合には、抽象的な表現、気分的な表現、生活的な表現、栄養補給の表現、現状維持の範囲での表現などを使って言い換えることがポイントです。
【具体例】
・「腸内環境が良くなって便秘が解消」「宿便デトックス」
=身体症状の改善で医薬品的な効果効能なのでNG
→「毎日の健康維持に」という抽象的・現状維持の表現に言い換えOK
「朝からスッキリ爽快」「軽やかに元気」という気分的な表現に言い換えOK
・「痩せて細くなる」「内臓脂肪を燃焼してメタボ解消」
=身体の変化を示す医薬品的な効果効能なのでNG
→「燃えるあなたへ」「気分リフレッシュ」という気分的な表現に言い換えOK
「ダイエットをサポート」「ファスティング時に足りない栄養素を補給」という栄養補給の表現に言い換えOK
(3) 保健機能食品の種類と表現規制
① 保健機能食品とは何か
上記の一般食品と異なり「血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています」「内臓脂肪を減らすのを助けます」など、健康の維持・増進に役立つ食品はその機能について、また、国の定めた栄養成分について一定の基準を満たす場合はその栄養成分の機能について表示することができます。
このような機能性の表示ができる食品を「保健機能食品」と言います。
保健機能食品には特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。
保健機能食品は、医薬品と異なり疾病の治療・予防のために摂取するものではないので、たとえ実際に効果があったりエビデンスがあったとしても、「医薬品」と誤認を与えるような表現は、薬機法に抵触するおそれがあるので注意が必要です。
②「特定保健用食品(トクホ)」における表現の注意点
特定保健用食品とは、健康の維持・増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ「おなかの調子を整える」「コレステロールの吸収をおだやかにする」などの表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可していて、許可証票(トクホマーク)を表示できます。
特定保健用食品であっても、医薬品と異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではないので、「糖尿病の疑いがある貴方へ」「花粉症が治ります」など疾病の予防や治療的な表現はNGです。
糖尿病の予防であれば「食後の血糖値の上昇をおだやかにする」、花粉症であれば「目や鼻が気にならなくなる」といった表現に言い換えるとよいでしょう。
③「栄養機能食品」における表現の注意点
栄養機能食品とは、1日に必要なビタミンなどの栄養成分が不測しがちな場合、その補給のために利用できる国の規格基準に適合した食品です。
栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制で、国によって決められた成分の量が含まれていれば、栄養成分の機能を表示できます。
機能の表示をすることができる栄養成分は、脂肪酸(1種類)、ミネラル(6種類)、ビタミン(13種類)に限定されています。
栄養成分ごとに表示できる内容は決められています。
例えばビタミンEの場合、「栄養機能食品(ビタミンE):ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。」のように、国が定めた定型文どおりに表示するよう注意が必要です。
④「機能性表示食品」における表現の注意点
機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報が消費者庁長官への届出られたものです。
トクホとは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けるものではありません。
機能性表示食品も、医薬品と異なり疾病の治療や予防のために摂取するものではないので、疾病の予防や治療的な表現はNGです。
機能性表示食品においては、機能性の成分・内容を広告表示することがOKなので、これを活用して訴求するとよいでしょう。
例えば、研究レビューにより科学的根拠が示された場合、「届出表示:本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンはBMIが高めな人の内臓脂肪を減らす効果があることが報告されています。」のように表示することで、対象者がBMIが高めな人であること、この製品に含まれる茶カテキンによって機能性があることをアピールできます。
(4) 薬機法違反のリスク
薬機法に違反した場合、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又は併科の刑事罰や、商品売上額×4.5%の課徴金納付命令を受ける可能性があります。
せっかく健康食品のビジネスモデルがあっても、薬機法の理解がなかったことで、上記のペナルティーさらには商品の販売中止・回収や信用の失墜などのリスクが考えられます。
(5) お気軽に弁護士にご相談ください
① 弁護士に相談するメリット
健康食品の製造・輸入・販売は、薬機法の他、健康増進法や食品衛生法等による規制を受けます。
また、表示方法や販売方法に関しては、景品表示法、食品表示法、JAS法、特定商取引法等の規制に従わなくてはなりません。
法律の専門家である弁護士であれば、健康食品に関連する数多くの規制法規に幅広く目配りして、事前のリスク防止からトラブル発生時における適切に対応いたします。
薬機法はじめ諸法の規制を正しく遵守して刑事罰その他のペナルティーやトラブルを避けるために、弁護士によるリーガルチェックを受けることをお薦めします。
② 森大輔法律事務所にできること
森大輔法律事務所は、開所10年来、薬機法や景表法など広告表示に関する法的問題のサポートに力を入れて取り組んでおります。事業内容や商品の種類に合わせて、薬機法や景表法における注意点について具体的なアドバイスを行っております。
(ア)法律相談~広告のチェック
薬機法についての疑問点やトラブルが生じた際はもちろん、その他の法令遵守や契約交渉・労務管理など、会社が直面する法律問題について幅広く相談することができます。
商品パッケージ、チラシ、HPなどの広告については、法的な問題がないか複数の弁護士によるダブルチェックを受けられます。表示事項、セリフ・ナレーションなどを丁寧に確認し、必要に応じて消費者の誤解を招かないよう注釈の追加や魅力的な言い換えの提案も受けられます。
(イ)研修セミナーを開催
広告担当者を対象とした薬機法や景表法のポイントを弁護士がわかりやすく伝える研修セミナーで、役立つ知識を獲得できます。
(ウ)消費者庁やマスコミへの対応
消費者庁による調査などトラブルが発生した場合、弁護士のサポートをスピーディに受けられます。
(エ)意見書の作成
商品パッケージやHHPなどの広告が薬機法や景表法に抵触していないか等について、弁護士に意見書の作成業務も行っております。
③ 24時間いつでも問い合わせOK!
森大輔法律事務所は、薬機法や景表法に関わる御相談や御依頼を10年間で数多くお受けし、インパクトある適正な広告づくりのサポートに力を入れております。
たとえば
・制作した広告に法的問題がないか不安で悩んでいる方
・この表現が法的に問題ないかを相談したい方
・経験豊富な弁護士に広告をチェックしてほしい方
・弁護士による「広告のための景表法セミナー」を受講したい方
・法務・労務トラブルの相談に加え広告チェックもできる顧問弁護士がほしい方
森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでも相談できます。
【相談はこちら】
薬機法や景表法に詳しい経験豊富な弁護士が喜んで対応します。
女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。
オンラインWeb会議ツール(ZOOM)を活用して、全国どこでも対応できます。
お困りのことがありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
-
お知らせ2026/02/06
-
お知らせ2026/02/06
-
お知らせ2026/01/22
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16