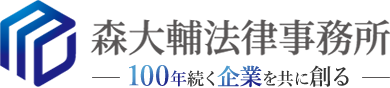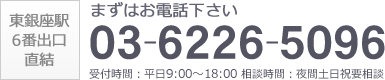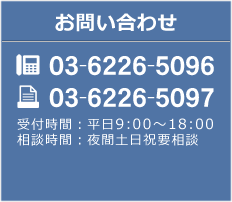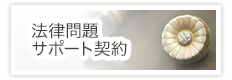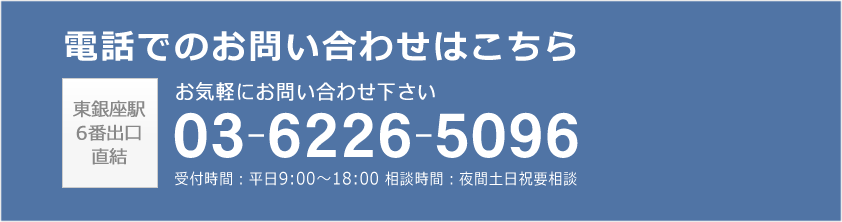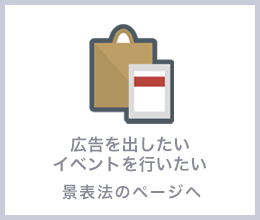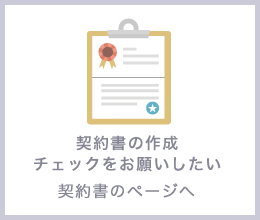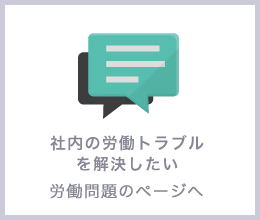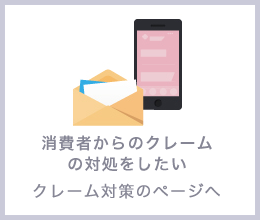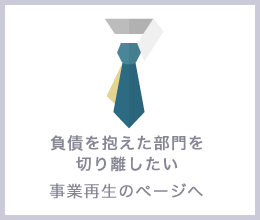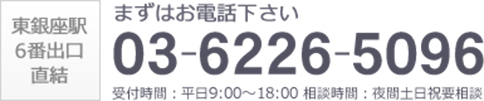従業員のメンタルヘルス不調は会社の責任?安全配慮義務違反とならないための対策について弁護士が解説
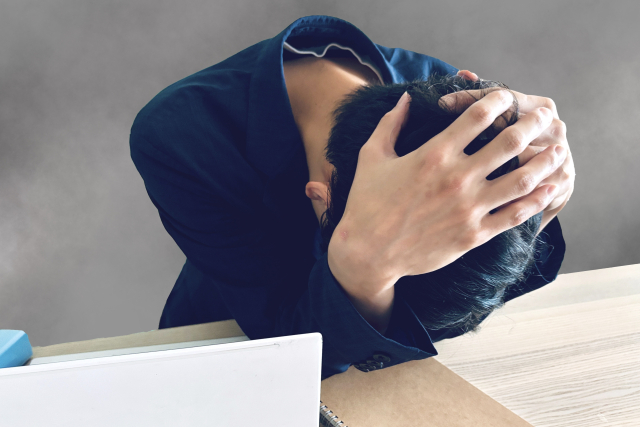
Contents
1.安全配慮義務とは?
会社は、従業員が生命・心身の安全を確保しつつ労働できるような配慮をすべき義務を負っています。
これを「安全配慮義務」といいます(労働契約法5条)。
具体的な内容としては、従業員が負傷することのないように工場の機器をきちんと整備したり、長時間労働による業務負荷を過度に生じさせないように配慮したり、セクハラやパワハラが原因となって従業員が心身の健康を害さないように快適な職場環境を整えたりすることです。
2.メンタルヘルス不調と安全配慮義務の関係
(1)メンタルヘルス対策も「安全配慮義務」のひとつ
会社が守るべき従業員の健康には、病気やケガ等の肉体的なものだけでなく、心の健康(メンタルヘルス)も含まれます。
したがって、従業員のメンタルヘルス対策も安全配慮義務のひとつです。
例えば、ストレスチェックの結果が悪い従業員には、心労やうつ病などの精神疾患が疑われます。
また、遅刻・早退・欠勤が多い従業員も、職場に何らかの不安を抱えていることが疑われます。
このようなメンタルヘルス不調の労働者を放置すると、会社は安全配慮義務に違反しているとして訴えられる等のトラブルに発展するリスクがあります。
(2)安全配慮義務違反の3つの基準
どのような場合に安全配慮義務に違反したことになるのか、その具体的な内容は法律で明確に定められてはいません。
実務上、安全配慮義務に違反するか否かは、①予見可能であったか、②結果回避義務を怠ったか、③これらと損害に因果関係があるか、の3つの基準によって判断されます。
要するに、会社が従業者のメンタルヘルスに問題が発生すると予見できたにもかかわらず、それを防ぐための努力を怠った場合に、①と②の基準を満たします。
そして、この努力を怠ったことが原因で、従業員に損害が発生したといえる場合、③の基準も満たし、会社は安全配慮義務に違反していると判断されます。
(3)裁判例
広告代理店に勤めるXが慢性的に長時間労働をしていて顔色や言動に明らかな異常があり、会社も状況を認識していたにもかかわらず、業務調整など必要な配慮を行なわず、その結果、Xはうつ病を発症して自殺した事案において、最高裁は、会社は安全配慮義務に違反したと判断して損害賠償を命じました(平成12年3月24日判決・電通事件)。
3.会社が取り組むべき具体的なメンタルヘルス対策
(1)メンタルヘルス対策の具体例
安全配慮義務として会社に義務づけられているのは、従業員に「危険や健康障害が生じる可能性が予見できたときは、その防止対策を講じること」です。
会社が安全配慮義務を果たすために、従業員のメンタルヘルス対策は欠かせません。
ただ、メンタルヘルスの不調はプライバシーに属する情報であるため、従業員が会社に申告しないことも少なくありません。
しかし、会社は、たとえ従業員本人からメンタルヘルスの不調について申告がなかったとしても、従業員のメンタルヘルスにかかわる労働環境等に十分な注意を払う義務があります。
ストレスチェックの悪い結果、遅刻・早退・欠勤の状況、同僚や上司からのメンタルヘルス不調を懸念する情報提供などを通じて、速やかに従業員のメンタルヘルス不調を察知し、例えば、産業医との面談を実施したり、業務量を軽減したり、休職を提案したりする等の対策に取り組んで、従業員のメンタルヘルスのケアに努めるとよいでしょう。
また、メンタルヘルス不調の原因となるパワハラ・セクハラ・マタハラ等のハラスメント、嫌がらせ、過重な業務、慢性的な長時間労働などを発生させないことが根本的な対策となります。
これらを発生させないためにメンタルヘルスやハラスメントについて社内セミナー等で従業員が学べる機会を設け、従業員がメンタルヘルス不調について同僚・上司や産業医に相談しやすい社風を築いておくことが重要です。
(2)裁判例
頭痛や不眠の症状で精神科に通院し、神経症の診断を受けて薬を処方されていたにもかかわらず、それらの情報を会社に申告していなかった従業員Xが、月60時間を超える時間外労働を続けた結果、うつ病を発症して休職した事案において、最高裁は、①自らの精神的健康(メンタルヘルス)に関する情報は、従業員にとって自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課に影響し得る事柄として、通常は職場に知られることなく就労を継続しようとする性質の情報であること、②会社は、従業員からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っていること、③従業員にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合、会社は、メンタルヘルスに関する情報について従業員本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど従業員の心身の健康への配慮に努める必要がある、と判示しました(平成26年3月24日判決・東芝事件)。
4.安全配慮義務違反を問われないための実践的ポイント
(1)安全配慮義務違反を問われた場合のリスク
安全配慮義務違反について、罰則は設けられていません。
しかし、会社は民事上の責任を問われ、損害賠償金や慰謝料を請求される可能性があります。
また、労働災害に認定された場合でも、労災保険給付を超える損害は会社の負担となります。
従業員に後遺症が残ったり死亡した場合には、高額な損害賠償金を請求されるリスクがあります。
したがって、会社は、従業員のメンタルヘルスに関しても安全配慮義務を負っていることを自覚したうえで、実践的な対策に取り組むことが重要です。
(2)実践的ポイント
①ストレスチェックの悪い結果、遅刻・早退・欠勤の状況、同僚や上司からのメンタルヘルス不調を懸念する情報提供などを通じて、速やかに従業員のメンタルヘルス不調を察知し、例えば、産業医との面談を実施したり、業務量を軽減したり、休職を提案したりする等の対策に取り組むことによって従業員の心のケアに努めます。
②メンタルヘルス不調の原因となるハラスメント、嫌がらせ、過重な業務、慢性的な長時間労働などを発生させないことが根本的な対策となります。
日常的にメンタルヘルスやハラスメントについて社内セミナー等で従業員が学べる機会を設け、メンタルヘルス不調やその原因となっている出来事についても同僚・上司や産業医に相談しやすい社風を築きます。
③昨今におけるメンタルヘルス不調者の増加に対応するため、産業医を精神科医から選任したり、それが難しい場合には産業医が精神科医と連携できる体制を構築するなど、メンタルヘルス対策を強化します。
特に、従業員の主治医と産業医で意見が食い違った際、精神科医に相談できる体制が確立されていると安心です。
5.弁護士に相談するメリット
(1)弁護士への相談を勧める理由
法律の専門家である弁護士であれば、労務問題に関する数多くの法規や裁判例に幅広く目配りして、事前のリスク予防からトラブル発生時における交渉・労働審判・裁判・マスコミ対策までオールマイティに対応して問題を解決することができます。
(2)森大輔法律事務所は24時間いつでも問い合わせOK
森大輔法律事務所は、会社・経営者側に特化して労務トラブルに対処できる法律事務所としてスタートしました。
10年間で労務トラブルに関する御相談・御依頼を数多くお受けして、問題社員の解雇、ハラスメント、労働審判、団体交渉への対応など幅広い労務問題への対応に力を入れて取り組んでおります。
したがって、メンタルヘルス不調の従業員への対応はじめ、実際の具体的なケースに応じて、会社・経営者側の立場で適切な対策をとることができます。
・メンタルヘルス不調の従業員への対応に苦慮されている方
・社内で発生した労務トラブルに頭を悩ませている方
・弁護士によるハラスメント対策セミナーを社内で開催・受講したい方
・幅広い法務・労務の相談にスピーディで親身に対応できる顧問弁護士がほしい方
森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでも相談できます。
【相談はこちら】
労務トラブルに詳しい経験豊富な弁護士が喜んで対応します。
女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。
オンラインWeb会議ツール(ZOOM)を活用して、全国どこでも対応できます。
お困りのことがありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
※会社・経営者側専門となります。従業員(労働者)側のご相談は現在、受け付けておりません。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
-
お知らせ2026/02/06
-
お知らせ2026/02/06
-
お知らせ2026/01/22
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16