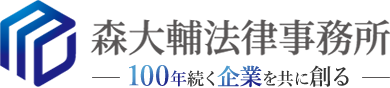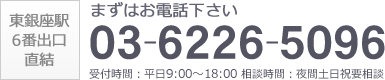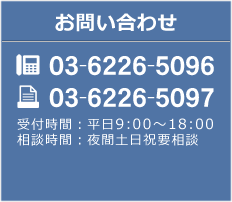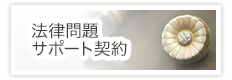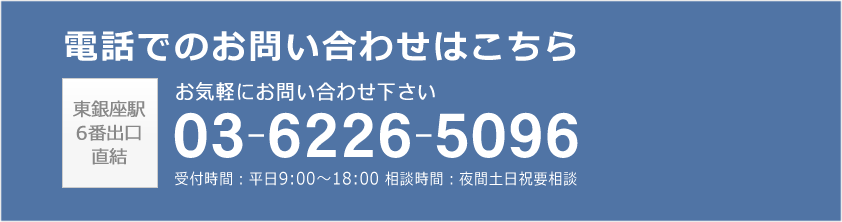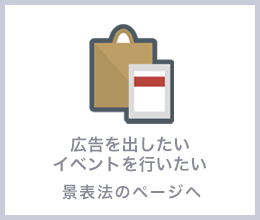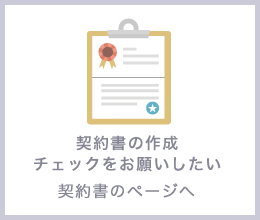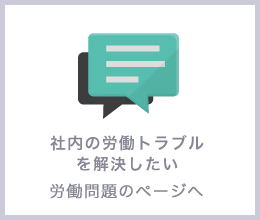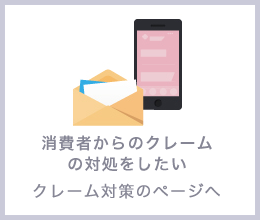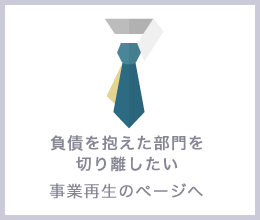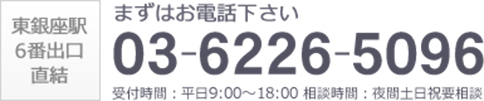未払い工事代金の回収方法を弁護士が解説

Contents
1 なぜ工事代金の未払いが生じるのか?
建設業・解体業の事業者さんが工事代金を請求したときに、施主さんや元請などからいつまで経っても支払いがなされないというケースがあります。
支払いがなされない原因は様々であり、たとえば、建物の構造が図面と違ったため追加工事が発生した、契約書がなかったため金額の算出方法について双方の認識が異なっていた、などのケースも考えられます。
しかしながら、圧倒的に多いのは、相手方に支払能力がないため支払えない、というケースだと思います。
ひとえに支払能力がないケースと言っても、様々な段階が考えらます。
すなわち、他にも支払いがたまっているため解体工事費用の支払いを後回しにしているケースから、既に破産状態にまで至っておりどうにも支払いができないケースまで考えられます。
ただ、どのような段階であっても、早期に回収に着手するということが重要になります。
2 弁護士から「支払い通知書」を出すことにどのような意味があるか?
(1)相手方の反応がある場合
弁護士が建設業・解体業の事業者さんから工事代金の回収を依頼された場合、まずは、弁護士名義で相手方に支払いを求める通知書を出します。
弁護士名義で「支払い通知書」を郵送すると、相手方がすぐに支払ってくるケースもそこそこあります。
また、なぜ支払いをしないのか理由を明らかにしてくるケースがあります。
相手方が支払いをしない理由が明らかになれば、こちらも反論をすることができます。
そして、相手方がこちら側の主張に合理性があると判断してくれれば、工事代金を支払ってくれるケースもあります。
その一方で、双方の言い分が平行線のままであれば、裁判に移行せざるを得ません。
ただ、このようなケースで裁判に移行しても、相手方の支払能力に問題がないのであれば、回収の可能性は高いと思います。
(2)相手方の反応がない場合
問題は、相手方が弁護士からの「支払い通知書」を受領したにも関わらず、何ら反応をしないケースです。
これは、工事代金の金額に特に争いがないものの、相手方に支払能力がないため無視せざるを得ないというケースです。
ない袖は振れぬと言いますが、このようなケースが一番対応に苦慮するケースになります。但し、債務名義(判決)は取得しておき、いつでも強制執行が出来る状態にしておくことは重要です。
(3)まとめ
弁護士が「支払い通知書」を出すことによって、一定の割合で支払いがなされます。
たとえ支払いがなされなかったとしても、相手方がどのような理由から支払わないのかが明確となり、今後の方針を決めるにあたって重要なヒントとなります。
したがって、弁護士から「支払通知書」を出すことは、今後の方針を見極めるために重要な意味があるのです。
3 留置権は工事代金の回収に役立つか?
(1)建物の留置権
建設業には建築業務も含まれているので、建物を建てる工事をすることもあります。
建物を建てて完成させたのに工事代金を支払ってくれない場合、建物について留置権(民事留置権)が発生します。
したがって、建物を建てる工事の場合は、「工事代金を支払ってくれるまで、建物の鍵を渡さない!」という主張をすることも理論上可能です。
こうすることによって、建設業者に優先的に支払いをしなければならないという心理的プレッシャーを与えることができます。
(2)建物の敷地の留置権
なお、建物の敷地まで占有できるかという議論があります。
これは、商事留置権の成否という論点になりますが、商事留置権は民事留置権と異なり成立要件として牽連性が必要とされておりません。
また商人同士ではないと適用がないため、事業者同士の場合に限定されます。
そのため、建物の建築工事と牽連性がない土地についても商事留置権が成立するのかが問題となるのです。
この点について最高裁判例はなく、学説的には否定説が強く主張されています。
背景には、もし土地の占有を許してしまうと、土地に抵当権を設定している抵当権者を不当に害してしまうという考えがあるようです。
そのため、土地には商事留置権は成立しないと考えるべきです。
そうであれば、建物の敷地を占有して工事代金を回収するということは難しいと思います。
(3)解体業の場合
解体業の場合は、建物を壊して更地にしてしまうため、建設業のように建物についての留置権を主張するという手法は期待できません。
上記の商事留置権の議論からしても、解体をしてその更地(元々の建物があった敷地)を引き渡さないということは、基本的に主張できないと考える方がよいと思います。
そのため、ケースにもよりますが、建設業と比べて解体業の方が工事代金の回収が困難になるリスクがより高いといえるでしょう。そのため、どれだけ早く回収手続きに進めるかがポイントとなります。
4 工事代金を回収する裁判はどのように進んでいくか?
(1)金額に争いがなく相手方が欠席の場合
弁護士が「支払い通知書」を送っても相手方が支払いに応じない場合、裁判をすることになります。
請負工事代金の金額に争いがないような事案であれば、相手方が裁判に出席せず、1回で裁判が終わることもあります。
この場合は、勝訴判決をもらった後にどのように回収していくのか、強制執行の問題になります。
(2)金額に争いがなく相手方が出席した場合
他方、金額に争いがない事案であっても、相手方が裁判に出てくることもあります。
このような相手方は支払う意思をもっている可能性がありますので、交渉次第では分割払などで回収できる見込みがあります。
(3)相手方が争ってくる場合
次に、工事の範囲や内容に争いがある場合です。
こちらは、裁判が終わるまで、ある程度の長い期間がかかります。
ただ、こちら側の主張に十分な合理性が認められるケースでは、最終的には判決+強制執行ではなく和解で回収できる可能性が高いと思われます。
解体業や建設業の裁判は、裁判中の和解によって解決するケースが多いです。
したがって、裁判を提起すること自体が、工事代金を回収する方法の一つとして意味があるといえるでしょう。
5 強制執行による回収方法
(1)銀行口座の差押え
裁判をしても和解などで工事代金の回収ができなかった場合は、強制執行をしていくことになります。
まずは、相手方の銀行口座を差し押さえることを検討します。
銀行口座の差押えは書面での申立てだけでできますので、簡易に回収ができる方法の一つです。
ただ、銀行口座がどこにあるのかが分からないケースも多く、そのような場合は弁護士会照会などの方法で調査することになります。
(2)現金の差押え
また、会社にある現金などを差し押さえる動産執行という方法もあります。
こちらは、現金を扱っている相手方であれば、効果が期待できます。
(3)不動産の差押え
さらに、相手方が不動産も所有しているようでしたら、不動産を差し押さえて換金することで工事代金を回収することが可能です。
6 要注意!工事代金回収の時効とは?
(1)5年で時効消滅
現行の民法において、請負工事代金の消滅時効は、代金支払期限から5年です。
(ただし、工事請負契約が2020年(令和2年)3月31日以前に成立している場合、旧民法が適用されるので時効は3年。)
したがって、代金支払期限から5年(または3年)を経過するまでに工事代金の回収ができない場合、時効更新措置がなければ消滅時効が成立して回収できなくなってしまいます。
(2)時効更新措置
時効更新措置をとると、それまでに経過した時効期間をリセットできます。
工事代金の時効更新措置としては、①相手方に支払義務を認める書面を書かせる方法、②相手方に未払い工事代金の一部を支払ってもらう方法などがあります。
7 工事代金の未払い問題は弁護士にご相談を!
(1)工事代金の回収を弁護士に相談するメリット
ア.上記の時効更新措置は、あくまでもそれまでに経過した時効期間をリセットするものにすぎません。
一般に、工事代金の未払いは、時間が経過すればするほど相手方の資力が悪化していくことが予想されるため回収が難しくなります。
工事代金が未払いのまま支払期限を過ぎてしまった時点で、早めの対応をとることが大事です。
たとえ時効更新措置をとった場合でも、「時効まで5年もある」といって安心せず、速やかに回収に向けたアクションを起こすこと、具体的には弁護士に相談して回収を依頼することを推奨します。
弁護士に工事代金の回収を依頼すると、弁護士が「支払い通知書」を作成・発送し、弁護士が窓口となって支払交渉をします。
したがって、代金回収に頭を悩ませる無駄な労力・時間・ストレスから解放されて、安心して本業に専念できるというメリットがあります。
イ.交渉による支払がなされない場合、弁護士であればスムーズに工事代金回収のための裁判手続に進むことができます。
一般的には、発注者の財産を仮差押えして、裁判で勝訴判決を得て、強制執行(差押え)によって回収する、という流れになります。
ただし、事案によっては、他の法的手段をとる方が適切であることもあります。
債権回収の経験が豊富な弁護士であれば、事案をしっかり分析したうえで、その事案に最適な方針で回収のために動いてくれます。
したがって、弁護士に相談・依頼すると、代金を回収できる可能性が高まるというメリットがあります。
(2)森大輔法律事務所は債権回収に力をいれています
森大輔法律事務所は、企業法務をサポートする事務所としてスタートし、多くの建設業・解体業の事業者さんから未払い工事代金の回収に関する御相談や御依頼を10年間で数多くお受けし解決してまいりました。
これまで債権回収に成功した実績の一部をホームページで解説しておりますので、ぜひご覧ください。
当事務所の債権回収の実績 | 森大輔法律事務所
森大輔法律事務所では、債権回収の実績ある弁護士が、工事代金回収のために「支払い通知書」の作成・発送、弁護士が窓口になっての交渉、最適な裁判手続の御提案・進行をスピーディーにおこなうので、債権回収に関するお悩みを大きく減らすことができます。
これに加えて、森大輔法律事務所は、代金未払トラブルを未然に防止するための事前サポートにも力を入れております。
具体的には、複数の弁護士によるダブルチェック体制で、「請負契約書」はじめ契約時に使用する書類の整備、取引先から受け取った契約書案のリーガルチェック、日常業務で生じた法的な問題のご相談に、スピーディーかつ親身に対応しております。
また、森大輔法律事務所では、解体業者さん向けに、債権回収プラン(月額3万3千円の顧問料〈債権回収のみの顧問料〉で、地方裁判所での裁判における着手金が工事代金の回収金額の大小に関わらず税込11万円)をご用意しております。
詳細は、債権回収定額パック(債権回収をご希望の方) | 森大輔法律事務所 をご覧ください。
・工事代金をどのように回収すればよいか分からず悩んでいる方
・代金回収を弁護士に任せて無駄な労力・時間・ストレスから解放されたい方
・弁護士に相談・依頼してスムーズに代金回収をしたい方
・ネットで見つけたひな型や標準約款をそのまま使っていて不安がある方
・「債権回収定額パック」の利用を検討したい方
・トラブルへの最適な対応のみならず、トラブルを未然に防ぐサポートを日常的に親身かつスピーディーにしてくれる顧問弁護士が欲しい方
森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでも相談できます。
【相談はこちら】
債権回収の経験豊富な弁護士が喜んで対応いたします。
女性弁護士を含むチームによる対応も可能です。
オンラインWeb会議ツール(ZOOM)を活用して、全国どこでも対応できます。
現にトラブルが起きている、事前の防止策を整えたいなど、お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
債権回収プランの詳細はこちらになります
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
- 「弁護士が教える低評価の Google クチコミにオーナー返信をする際のポイント」の記事を追加しました。 - 2026年1月13日
- 「薬機法とは?規制概要や薬事法との違い、違反した場合の罰則について弁護士が解説」の記事を更新しました。 - 2026年1月8日
- 「労働基準監督署(労基署)に通報されたら会社はどうなる?企業がとるべき対応について弁護士が解説」の記事を追加しました。 - 2025年12月25日
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16
-
弁護士コラム2025/11/26
-
お知らせ2025/11/25
-
お知らせ2025/11/14