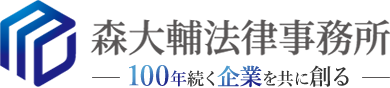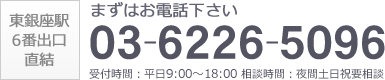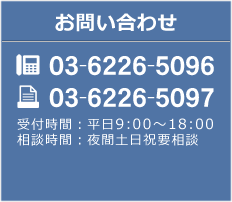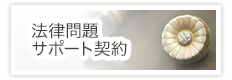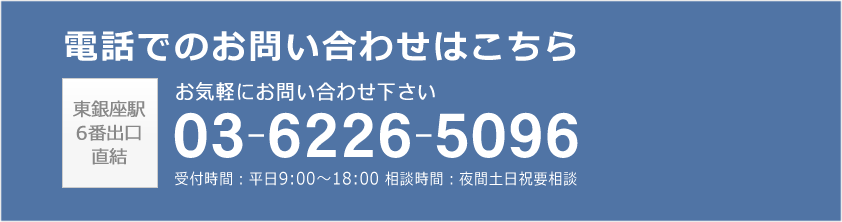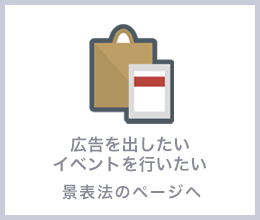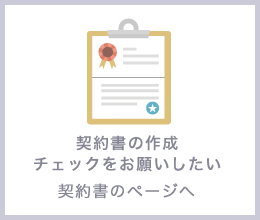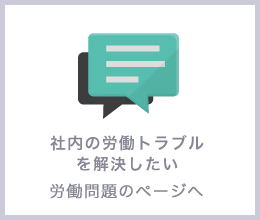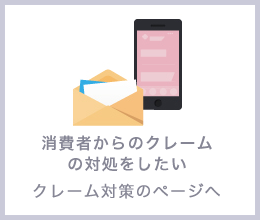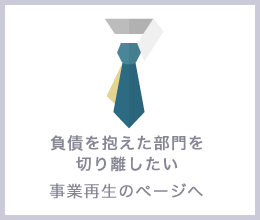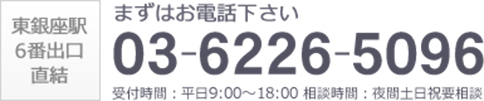解体業と外国人の雇用に関する法律の基礎知識を弁護士が丁寧に解説

Contents
1.はじめに
厚生労働省によると、日本で働く外国人労働者は2024年10月末時点で230万人を超えて過去最多となりました。
近年、解体業界でも、解体工事の需要が高まっている反面で熟練工が高齢化し若年層の新規参入が少なく深刻な人手不足が生じている状況ゆえに、外国人労働者を雇用するケースが増えています。
外国人労働者の雇用は、人手不足を解消できるだけでなく、異文化の新しい視点がもたらされて解体工事の効率化に貢献している例も見られます。
しかし外国人労働者の雇用には、日本人を雇用する場合とは異なる法律上の注意点が多数あるため、悩みやトラブルが生じやすいです。
本記事では、解体業の事業者が悩みがちなポイントを中心に、法律の基礎知識と実務的な対策について弁護士が解説します。
2.外国人の雇用に必要な「在留資格」の確認
(1)在留資格と就労可能な業務範囲
解体業において外国人労働者を雇用する場合、まず最も重要なのは「適切な在留資格」を持っているかの確認です。
在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)によって29種類に分類されており、それぞれの資格ごとに就労可能な業務範囲や条件が細かく定められています。
技能実習生が代表的ですが、業務範囲外の労働をさせることはできません。
外国人労働者を雇用する場合には、その外国人が業務内容に適した在留資格を有していることが重要です。
解体業で外国人を雇用する場合に関係するのは、主に以下の在留資格です。
ア. 技能実習
「とび職」や「型枠解体工」といった特定の職種に従事できます。
なお、2024年6月21日公布の法改正により、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度は廃止されて、日本の人手不足分野における人材育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されることが決まりました。2027年から施行される予定です。
イ. 特定技能
2019年に新設された在留資格。
特定技能1号「建設」に解体工事が含まれ、解体工事の即戦力になります。
ウ. 永住者、定住者、日本人の配偶者
就労制限がないため解体工事を含むあらゆる仕事が可能です。
エ. 技術・人文知識・国際業務
解体工事における通訳や現場管理など専門的知識や技能を活かした業務に従事できます。
解体現場の作業員としての就労はNG。
(2)不法就労
日本において、外国人労働者が適切な在留資格を持っていなければ「不法就労」となります。
例えば、在留カードを偽造した密入国者、在留資格の期間切れの者、退去強制が決まっている者など、在留資格を持たない外国人を働かせることは不法就労に該当します。
また、出入国在留管理庁から認められた範囲と異なる業務をさせる場合も、不法就労に該当します。
不法就労者を雇用していたことが判明した場合、事業主は不法就労助長罪(入管法73条の2)として処罰されます。
外国人を雇用する際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合には、処罰を免れません。
(3)経営者がすべき対策
ア. 採用時
必ずオリジナルの在留カード原本を確認します。コピーや写真だけでなく、実物を目視確認することが重要です。
在留カードで特に確認が重要なのは、就労制限の有無、有効期限、資格外活動許可の有無です。
在留資格と就労させる業務内容がきちんと合致しているかを確認することが重要です。
外国人の採用が決まった場合には、労働施策総合推進法により外国人雇用状況の届け出が義務付けられているので、ハローワークへの届け出が必要です。
イ. 採用後
定期的に有効期限を確認し、期限切れにならないよう管理を徹底して、適宜、更新手続の案内やサポートをすることが必要です。
もし、不法就労が発覚した場合は、直ちに就労を停止させて、出入国在留管理庁または専門家(弁護士・行政書士)にご相談ください。
3.言語・コミュニケーション問題
(1)労働条件の明示
ア. 外国人労働者に労働条件を理解させる必要性
労働基準法3条は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをすることを禁止しています。
すなわち、外国人労働者にも日本人と同様に労働関係法規が適用されます。
労働基準法、最低賃金法、老翁安全衛生法、労働災害補償保険法、雇用保険法、労働契約法、厚生年金保険法など労働者の権利を守る法律は、国籍に関係なく適用されるのが原則です。
ただ、日本人にはあたりまえ暗黙のルールであっても、文化や風習の異なる外国人には通用せずトラブルに発展することも多くあります。
外国人の文化や風習に配慮するために合理的な範囲内で日本人と異なる取扱いをすることは可能なので、外国人と雇用契約を結ぶ際には労働条件を意図したとおりに理解してもらえるよう一工夫して対策することが大切です。
イ. 経営者がすべき対策
経営者としては、外国人と雇用契約を結ぶ際、日本人を雇用する時よりも分かりやすく労働条件を明示して書面で交わすことで対策をすべきです。
とくに、①業務内容、②研修の有無、③労働時間、④休日・休暇、⑤所定労働時間外労働や休日労働の有無、⑥税金・社会保険料・控除内容などについては、あたりまえと思われることでもしっかり説明して理解してもらう必要があります。
あわせて、在留資格が取得できなかった場合の対応についても明記しておくことが重要です。
また、危険を伴う作業が多い解体工事の性質上、労働災害が発生した時の治療費や休業補償についてもわかりやすく説明しておくと良いでしょう。
外国人労働者本人が契約書の内容を十分に理解していることが重要なので、日本語が苦手な場合には契約書を母国語に翻訳して説明資料も提供することが必要になります。
(2)安全教育
ア. 外国人労働者に対する安全教育の重要性
解体工事は危険を伴う作業が多く、労働安全衛生法に基づく安全教育が重要です。
外国人労働者の労働災害による死傷者数は、2024年は全国で6244人にのぼり、解体業を含む建設業では1165人でした。
この背景には、経験が浅いことに加え、日本語が苦手で同僚とのコミュニケーションがうまくいっていなかったり、会社側の想定どおりに安全指示や作業方法が伝わっていない状況があります。
労働安全衛生法上、外国人に対しても適切な安全教育を実施する義務があります。
安全教育資料は、母国語または理解可能な言語で提供して、理解度を確認することが重要です。
マニュアルを読めない、理解できないなど言語の壁を理由に安全教育を怠っていると、災害発生時に安全配慮義務違反として会社が損害賠償責任を問われる可能性があります。
実際、ケガをした中国人が研修生として来日したもので日本語をほとんど理解できなかった事例において、作業手順や注意事項などについて中国語で記載した書面を交付するなどした上、その内容・意味を正確に理解していることを確認するのでなければ、安全教育としては不十分で安全配慮義務を尽くしているとはいえず、会社の安全配慮義務違反と事故との間に相当因果関係が認められるとして、損害賠償請求を一部認容した裁判例があります。
したがって、日本語が苦手で「普通こうする」が通用しない外国人労働者に対して、適切に安全教育をすることがとても重要です。
イ. 経営者がすべき対策
安全教育や指示は、理解できる言語で行なわなければなりません。
したがって、理解できる言語(ベトナム語や中国語など)でマニュアルを作成する必要があります。
たとえば、作業説明書にイラスト・写真やわかりやすい図解を用いると伝わりやすいです。
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の外国語に対応した動画やマンガ教材等を活用するとよいでしょう。
また、解体作業の現場においては、ピクトグラム(多言語対応の安全標識)で注意喚起したり、通訳できる先輩労働者や現場監督者を一緒に配置して母国語で安全指導や作業指示を理解できているか確認してから作業開始させる等して、安全を確保することが大切です。
(3)コミュニケーション体制
ア. 外国人労働者とのコミュニケーション不足を解消する必要性
外国人労働者の雇用に伴って生じやすいのが、文化や風習の違いによるハラスメントやトラブルの発生です。
日本人労働者のなにげない言動を外国人労働者がハラスメントと受け取ったり、外国人労働者の言動に解体現場の周辺住民が不快感を覚えてクレームを入れてくることがあります。
このようなハラスメントの多くは、コミュニケーションによるお互いに対する理解やリスペクトが不十分であることが原因です。
したがって、外国人労働者と日常的にコミュニケーションを図れる環境づくりが大切です。
イ. 経営者がすべき対策
このような事態を防ぐためには、日常的に翻訳アプリ(Google翻訳、Microsoft翻訳など)を活用したコミュニケーションを推奨して、日本の労働慣行についてわかりやすく伝えたり、日本人労働者が外国人の宗教や文化的背景に基づく習慣(食事、祈りの時間、安息日など)への理解を深めるなどして、意思疎通をスムーズにすることが重要です。
これによって、文化・風習の違いによるハラスメントやトラブルを防いで、日本人労働者も外国人労働者も不満を持たずに気持ちよく働ける環境を提供できます。
4.森大輔法律事務所は解体業者サポートに力を入れています
(1)お気軽に弁護士へご相談ください
外国人労働者の雇用に関する法律は、上記のように多岐にわたり複雑です。
外国人労働者の労務問題を得意とする弁護士に相談すれば、
・外国人労働者を雇用する際のトラブル対応
・雇用契約書やマニュアル作成についてアドバイス
・事故や労働災害が発生した時のサポート
・安全管理体制の問題点を検証し、法令遵守した改善策をアドバイス
など、多岐にわたるサポートを受けることができます。
これらのサポートによって、法的リスクを軽減して安心して本業に専念できます。
ご不明な点やトラブルが生じた際には、外国人雇用や労務問題に精通した弁護士へ早めに相談することをお勧めします。
(2)24時間いつでも問い合わせOK!
森大輔法律事務所は、日本各地で頑張る多くの建設・解体業者さまと顧問契約を締結して、100年続く建設・解体業の支援に力を入れております。
この10年でのべ100件以上、全国各地の建設・解体業者さまの御相談に乗り、トラブル対応、クレーム対応、建設・解体業者さまの代理人として交渉や裁判、工事代金の回収、顧問弁護士としての法律相談、請負契約書の作成、リーガルチェック等にたずさわって参りました。
森大輔法律事務所は、建設・解体業者さまが安心して本業に専念できるよう、多岐にわたる法的サポートを提供できます。
●外国人労働者への対応で悩んでいる方
●事故や労災への対応を弁護士に任せて本業に専念したい方
●日常業務のサポートに加え、事故が発生した時もサポートしてくれる顧問弁護士がほしい方
●建設・解体業に強い顧問弁護士を探している方
●「建設・解体業トラブルに関するセミナー」で学びたい方
森大輔法律事務所のホームページから24時間いつでも相談できます。
【相談はこちら】
建設・解体業の労務問題が得意な弁護士が喜んでスピーディに対応します。
女性弁護士を含むチームによる対応、オンライン(ZOOM)による対応もできます。
どうぞお気軽にお問合せください。
森大輔
最新記事 by 森大輔 (全て見る)
-
お知らせ2026/01/22
-
お知らせ2026/01/13
-
お知らせ2026/01/08
-
お知らせ2025/12/25
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/24
-
お知らせ2025/12/22
-
お知らせ2025/12/16
-
弁護士コラム2025/11/26
-
お知らせ2025/11/25